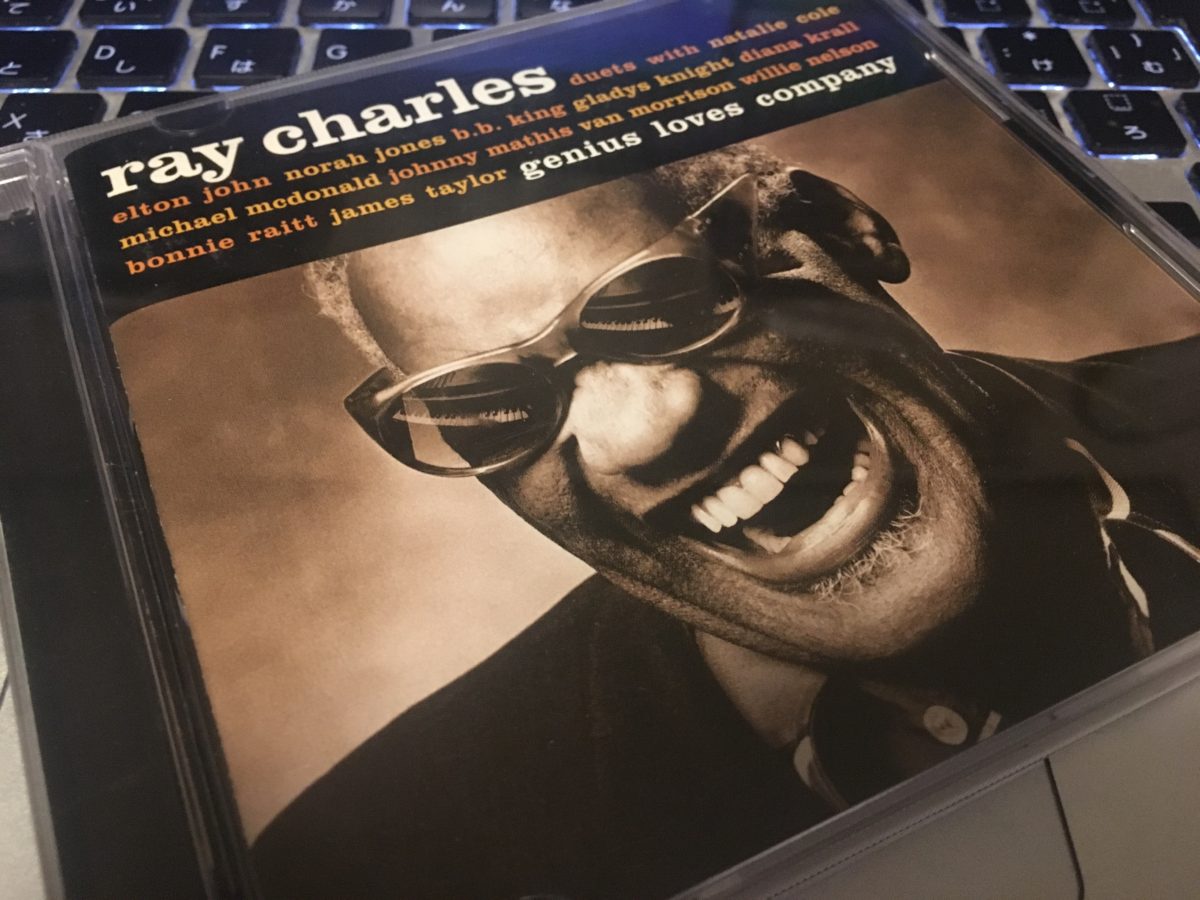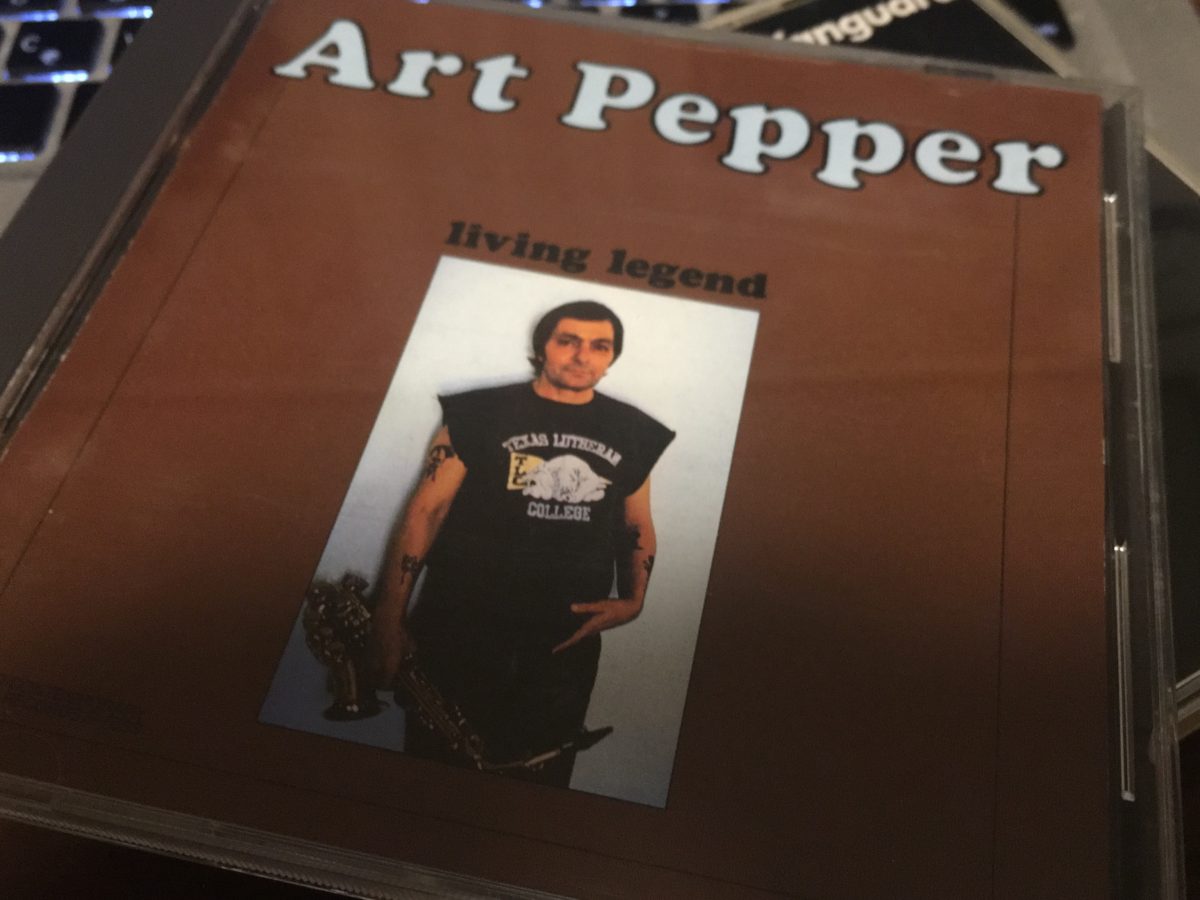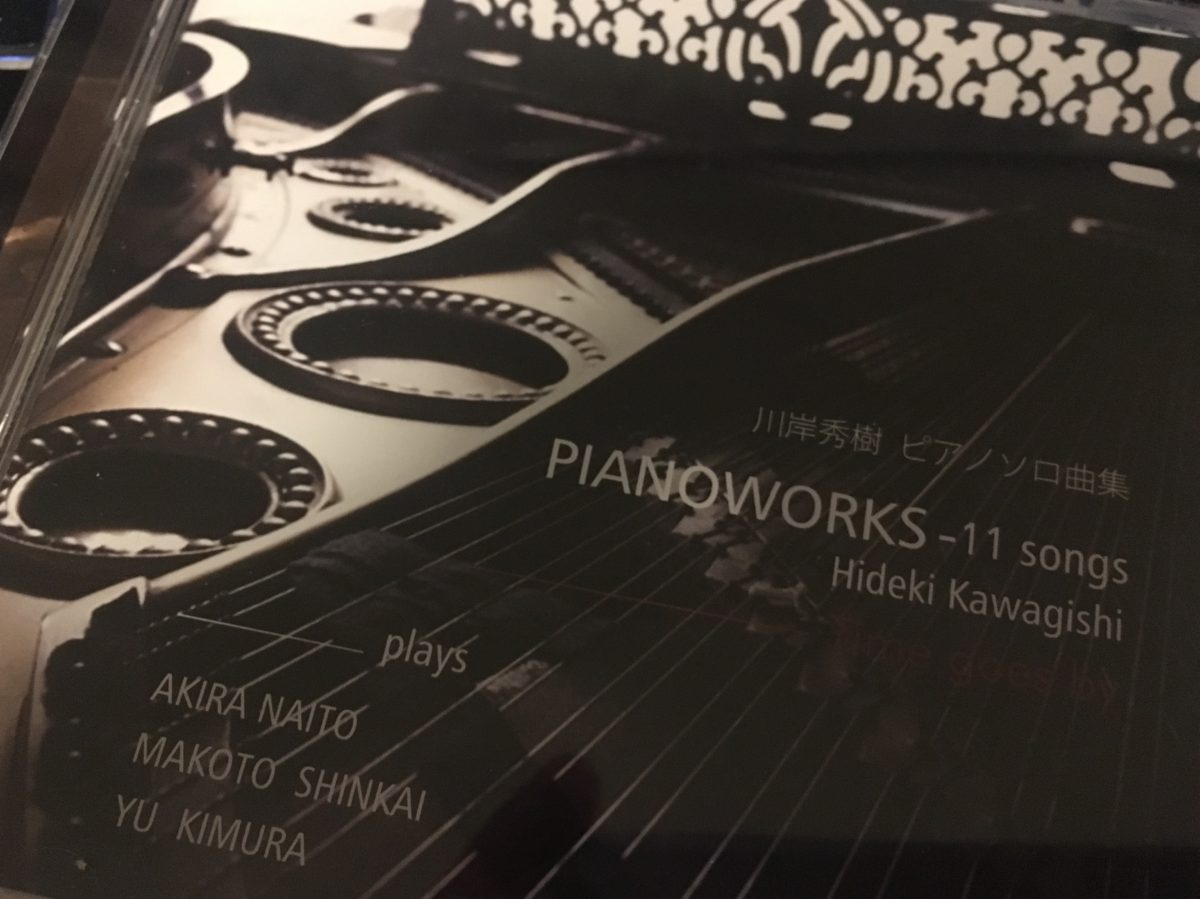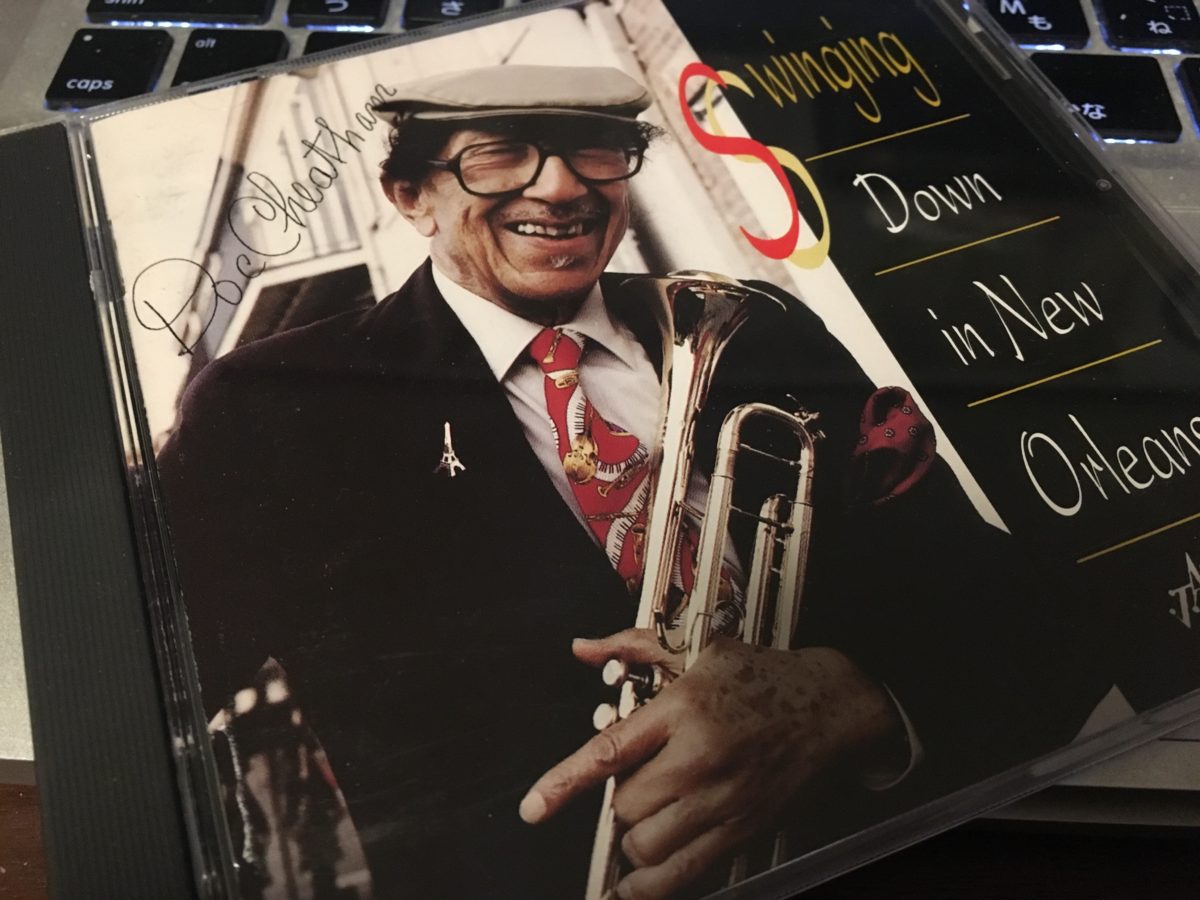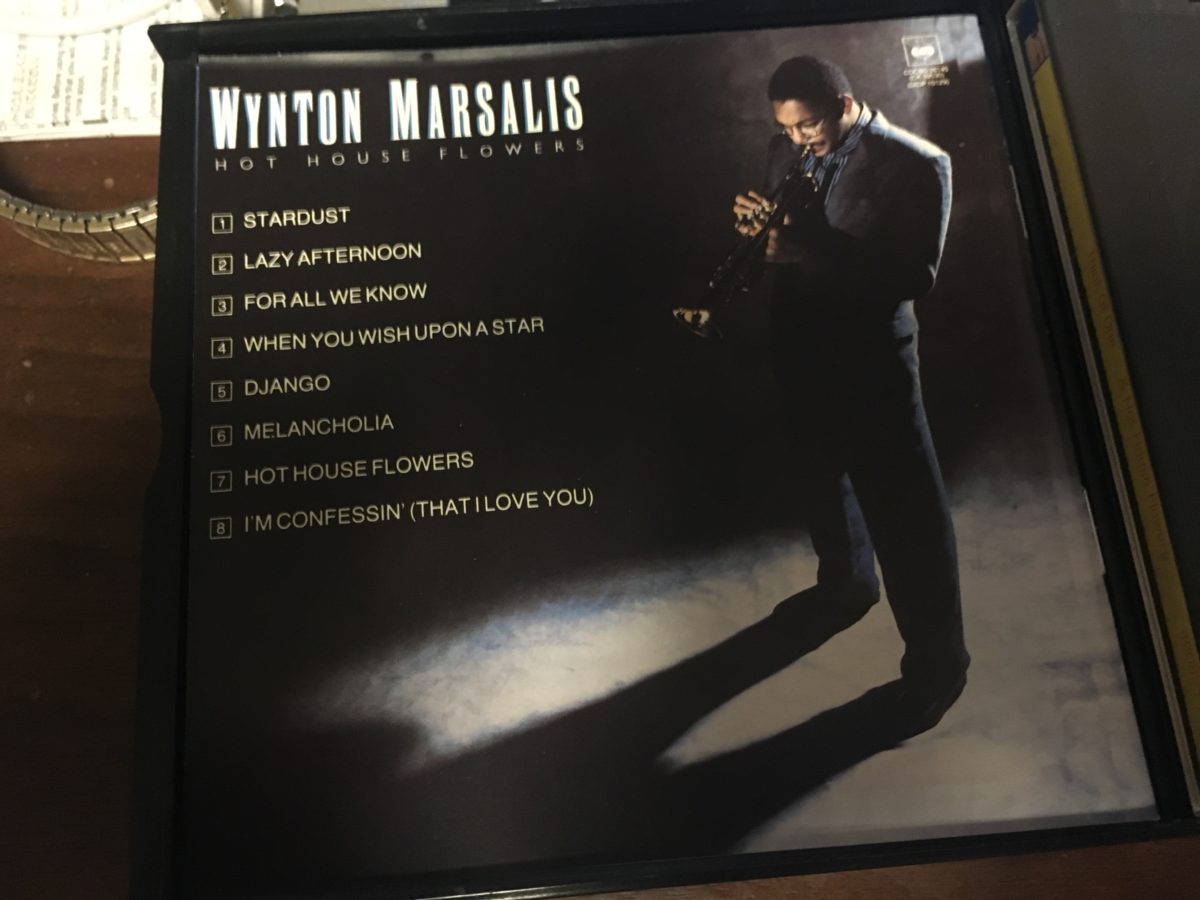生きていると、いろいろなことがあり、気分が浮かれたり、気分が沈んだりするものだ。ましてや、昨今のこの伝染病の流行る流行らないの毎日だと、気分が滅入ってしまう。私なんぞ、ここ二ヶ月ぐらいずっと気分が滅入っている。
なんと言おうか、ずっと頭の中に暗い影が残るようなそんな気分だ。楽しいことがないわけでもない。美味しいものを食べていないわけでもない。むしろ、楽しいことがあったり、買い物をしたり、美味しいものを食べたりは積極的にしているのだけれど、不思議とこの頭の中の暗い靄はいつまでも消えない。
いっそのこと、お祓いにでも行こうかとすら思っている。お祓いが効くか効かないかはとくに気にしていないのだが、そういうようなことをすると、なんだか少し踏ん切りがついて、本来すべきことや、本来感じるべき感情とかがなんとなく掴めるきっかけになるのではないかと思っている。
しかしまあ、お祓いをしたところで、どのくらいの解決になるかはわからないし、それまで待っていて何もしないと、どんどんネガティブな気分になってしまう。それでは、毎日がおもしろくない。そこで、一時的なカンフル剤かもしれないけれど、いろいろな音楽を聴いている。
ときにしみったれた音楽を、ときに軽快な音楽を、ときに荘厳な音楽をと考えているのだけれど、なかなか体と気分が付いてこない。そこで、その時その時聴ける音楽を聴くことにしている。無理して、聴きたくない音楽を聴けるほど人間は暇ではない。
今日は、少し軽快な、ウェスタンスイングを聴いている。Leon McAuliffeのバンドLeon McAuliffe & his Cimarron boysだ。
レオン・マックリーフは元々Bob Willsのプレイボーイズの中心人物だったスティールギタープレーヤーだ。4本ネックの凄い奴を自在に操って、ジャズでもカントリーでも、なんでもこなしてしまう。巧みにポジションを移動しながら、スティールギター独特のサウンドを鳴らしまくる。これだけで、ウェスタンスイング好きにはたまらない。
ボブウィルスのバンドも豪華な編成だが、レオンのバンドも同様に、フィドルやホーンセクションが入っていて、スウィングビッグバンドである。常に陽気で、それがちょっと疲れる時もあるのだけれど、ウェスタンスイングに暗いムードは似合わないのかもしれない。これはこれで、こういう音楽として成り立っているのだからよしとしよう。
ウェスタンスイングはカントリーミュージックの一つのルーツとも言えるけれど、むしろ一つの派生系と言ったほうが正しいのかもしれない。悲しいかな、日本のレコード屋には滅多に売られていない。こういう音楽を今更聴こうという人は本国アメリカでも少ないのかもしれないけれど、もっともっと見直されても良いジャンルの音楽だと思う。
日本でヴァイオリンときたら、十中八九がクラシック音楽で、ごく稀にジャズをやっている人がいるぐらい。ウェスタンスイングをやったり、ブルーグラスをやろうなどという人たちはごく少数だ。アメリカでは、ヴァイオリンといえば、クラシックのお坊ちゃん、お嬢ちゃんたちだけの楽器ではなくて、カントリーやら、ロックやらでもヴァイオリン(フィドルとか呼ばれているけれど)を弾いている人もそこそこいるのではないだろうか。
大草原の小さい家の、お父さんもフィドルを弾いたりしているし。アメリカのテレビの音楽番組ではマークーオコナーというヴァイオリニストが長年ホストを務めていたりする。マークーオコナーは、ブルーグラスプレーヤーだけれど、引かせようと思ったら、ジャズだろうと、ロックだろうと、ウェスタンスイングだろうと、なんだって弾ける。
スチールギターも、日本ではあんまり競技人口は多くないけれど、本国アメリカではまだそこそこ作っているメーカーがあるぐらいだから、盛んなのではないだろうか。5年ぐらい前にナッシュビルに出張で行った際に、ライブハウスでスチールギターを弾きまくっているお兄さんが居たから、そうに違いないと思っているのだけれど、実際のところどうなんだろう。
まあ、とにかくウェスタンスイングが、いかに盛んでも、いかに衰退していても、このLeon McAuliffeのアルバムを聴いていれば、いかに素敵な音楽かをわかってもらえるだろう。