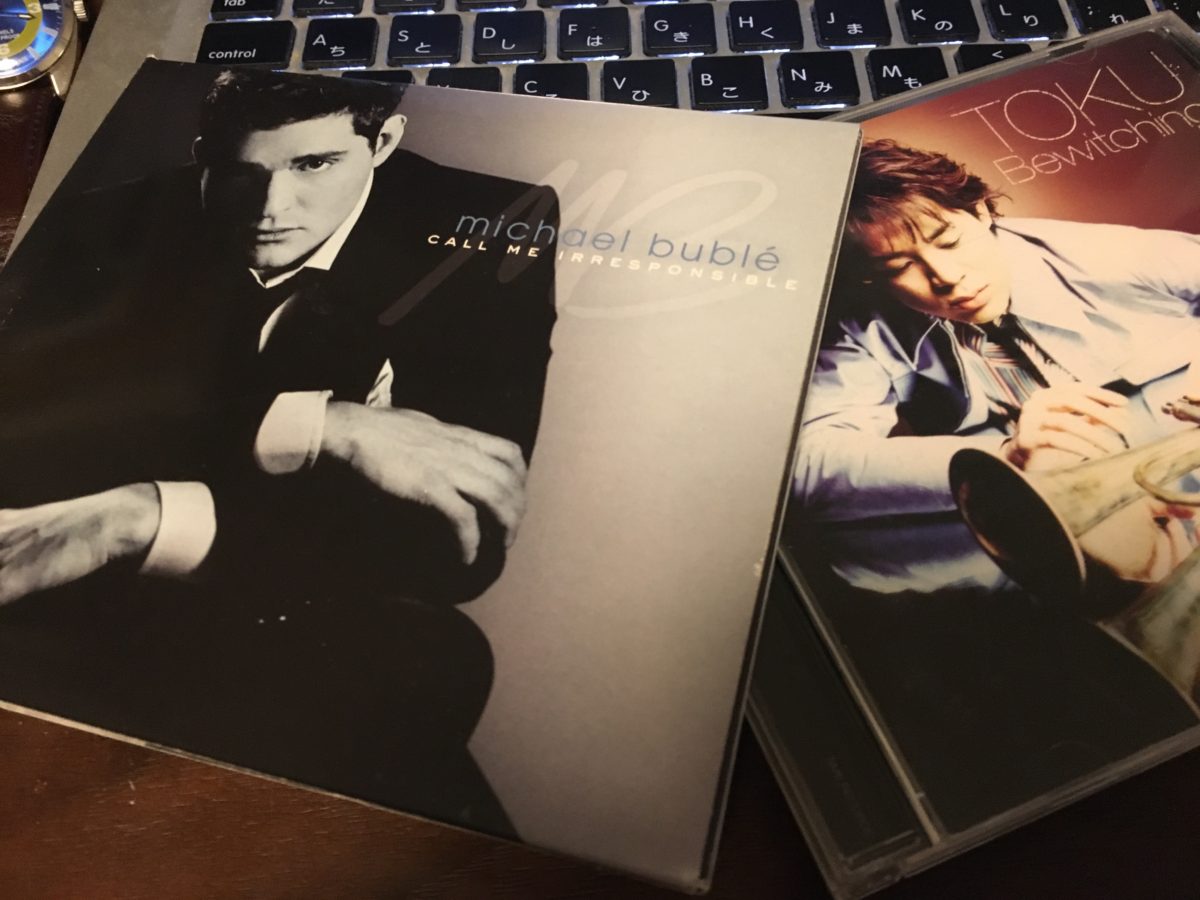トランペットのワンホーンカルテットの名盤は案外少ない。大抵は、もう一人サックスやトロンボーンが入っていて、ソロを回している。
サックスのワンホーンものはそれに比べたら少しは多いかもしれない。これは、トランペット好きとしてはなんとなく寂しい。トランペット一本でも十分フロントは務まるのだけれど、どうも世の中はそれだけでは満足しないような気分になる。
ライブ盤のワンホーンカルテットは比較的多いのだけれど、スタジオ盤となると、少なくなる。マイルスデイヴィスなんかは、結局ワンホーンカルテットのアルバムを作らなかったんじゃないか?いや、もしあったらごめんなさい。私のレコードラックにはマイルスのワンホーンもののアルバムはなかった気がする。
マイルスの場合は、テナーサックスとのハーモニーを使ってまるでオーケストラのような世界観を出すこともできるということもあって、あえてワンホーンもののアルバムを作らなかったのかもしれない。マイルスとコルトレーンのクインテットは、その代表例だ。いつも素晴らしい。
何年も前に、雑誌の記事で読んだのだけれど、オールマンブラザーズがデュアンオールマンと、ディッキーベッツのツインリードギターにしたのは、マイルスとコルトレーンを意識したからだとのことだった。オールマンの場合は、マイルスとコルトレーンともまた違ったレイドバックしたギターの絡みが面白いんだけれど、まあいいか。今日はそのことについては書かないでおこう。
そんな、数少ないトランペットのワンホーンカルテットの名盤を一枚紹介したい。いまさら紹介するようなアルバムでもないけれど。
ジョニー・コールズのリーダー作「The Warm Sound」。これが、なかなか素晴らしい。ピアノのケニー・ドリューもいい味を出している。
ケニードリューは、サックスワンホーンものの、デックスとかのアルバムでいい仕事をしているから、トランペットのバックでも手馴れたもんである。ケニードリューのピアノは、とくに特別なことはしないのだけれど、安定しているからいいのだろう。この人はいつも安定していて、ピアノトリオでも、危なげがないので、どうもわざわざレコードを買ってじっくり聴く気になれなかったりするのだけれど、あらためて聴いてみるとこれが、まさに理想的なジャズピアノでないか!
アルバム「The Warm Sound」に戻って、ここでのジョニー・コールズのトランペットをじっくりと聴いてみたい。ジョニーコールズはほとんどヴィブラートをかけない。マイルスデイヴィスもほとんどかけないけれど、50~60年代の流行りなのだろうか。チェットベーカーもヴィブラートはあまりかけない。ヴィブラートをかけないでジャズを吹くと、どこかモダンな雰囲気がただよってくる。逆に、40年代からのスタイルは、ヴィブラートをかけまくるからだろう。
ハーフバルブを多用するところもマイルスのようだ。トランペットの音はマイルスの音に似ているのだけれど、意識的にそうしているのかな。
しかし、一方で、小気味よくスイングしている感じがちょっとマイルスよりも古めかしくて、好感が持てる。スイングの仕方が素直、と言えばいいのか、どんどん飛び出すソロのフレーズも、マイルスの感じとは随分違う。マイルスよりも、もっとケニードーハムのようなハードバップに仕上がっている。
それでは、ジョニーコールズに個性がないように聞こえるけれど、確かにこの人は個性が強い人ではない。危なげなく、しっかりきっちり正統派のジャズを奏でる仕事人である。仕事人であるからこそ、いいアルバムを作れるのだ。
サウンドは実験的であればいいというものではない。マイルスは、常に実験的なアルバムを作り続けていたけれど、ジョニーコールズはそういうタイプのトランペッターではなかったのだろう。だからこそ、頑固にハードバップの名盤を作ることができて、実際に、この「The Warm Sound」のような名盤がうまれた。
まさに、ウォームで、楽しげなアルバムに仕上がっている。ブルース良し、スタンダード良し、バラード良しの3拍子が揃っているワンホーンの名盤です。