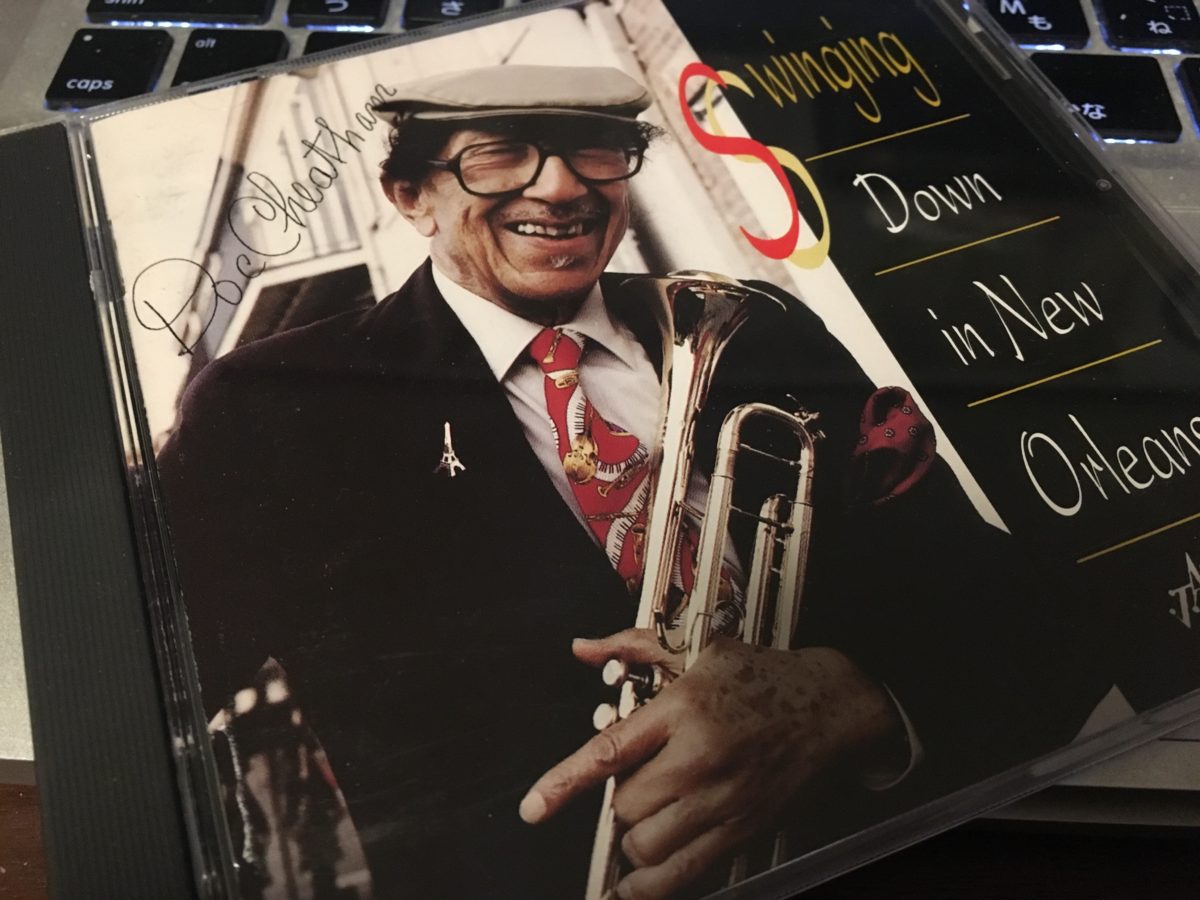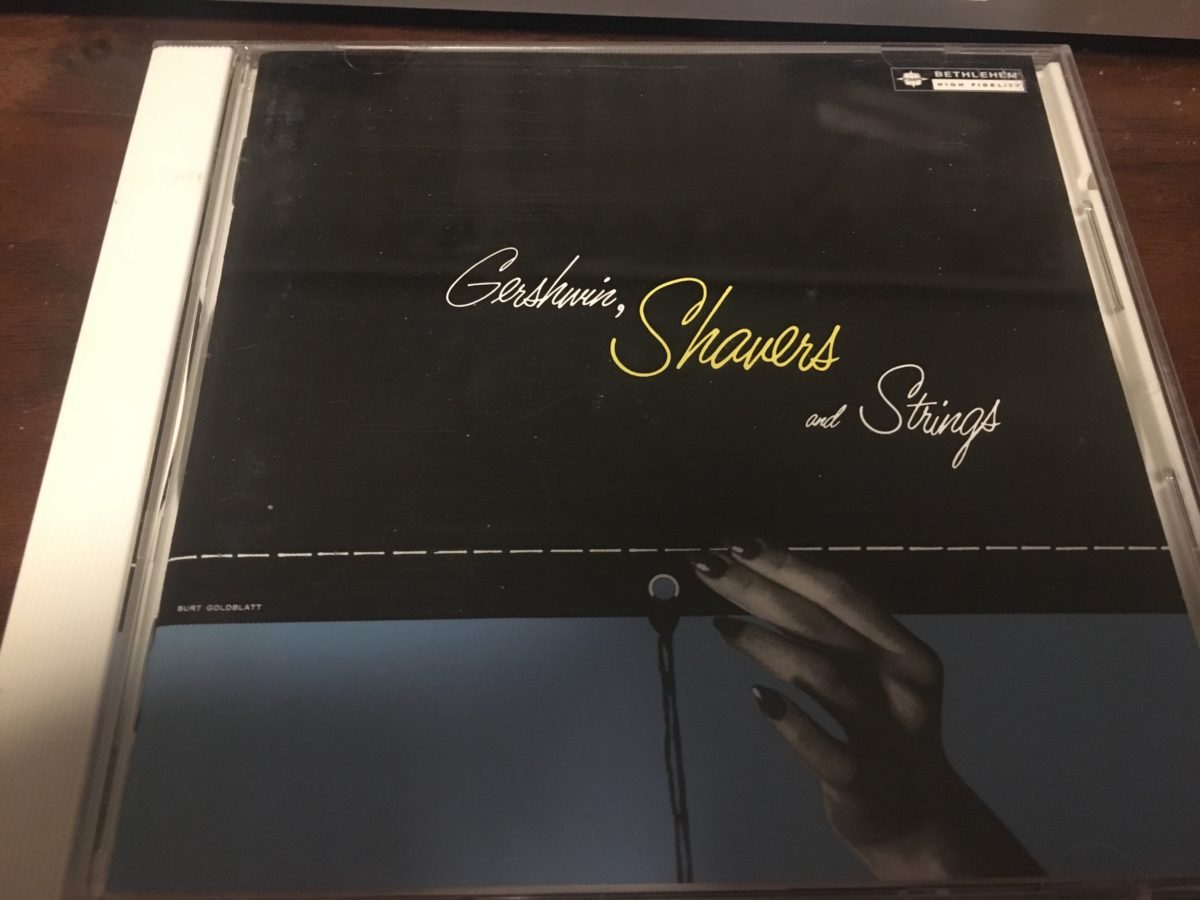また、買い物をしてしまった。
またしても楽器である。楽器の中でも相当な大物である。つい2週間ちょっと前にトランペットを購入したのだけれど、今度はトロンボーンである。
もう、今年は大きな買い物はしないようにしなければならない。今年は、もう楽器を買わないようにしなければならない。そう、心に誓おう。もう、1年分としては十分な楽器を買った。
第一、人間というのはそうやすやすと楽器を買うものではない。まあ、私みたいな楽器や稼業だと、人間がやすやすと楽器を買ってくれなければ成り立たないのだけれど。それでも楽器を買うというのは、ある種の特別な儀式みたいなところがあるので、楽器の購入を日常茶飯事に行ってしまってはいけない。あれは特殊な行事なのである。
そういう特殊な行事を、ひと月のうちに2回も行ってしまった。こういうことを頻繁に行うと脳がおかしくなるのではないか。ちょうど、悪習が身についている人や、何かの中毒患者のようになってしまうのではないか。だから、クールダウンが重要である。楽器を購入して、躁状態のときは、うまくクールダウンしなければならない。気をつけなければ。
それで、トロンボーンである。
トロンボーンの中でも、ジャズミュージシャン御用達のKingの楽器である。Kingの2Bという、それはそれは大定番である。その大定番のブラックラッカーという、変わり種である。初心者はまず手を出してはいけないような高級機種である。いや、高級というよりも上級者向けの楽器である。
吹けるのか?
いや、それが吹けないのである。
吹けないけれど、音は出せた。ポジションもなんとかわからないわけではない。トランペットでも普段はC譜で読んでいるので、トロンボーンもC譜で行ける(そもそもトロンボーンはC譜で読むのである)。
しかしまた、これが難しいのである。低い音は出せるのだが、1オクターブと少ししか出せない。思ったよりも音は簡単に出るのだけれど、音域を広げるのは、トランペット同様、とても難しい。
まあ、購入して二日目である。吹ける方がおかしいのだ。これで良いのである。仕方あるまい。
なぜ、トロンボーンを購入したか。これが一番大事なところなのであるけれど。ただ、トロンボーンという楽器を吹けるようになりたいという夢があったというと、なんだか嘘くさい。
はっきり言って、ずっとトロンボーンには興味は無かった。なんだか、トロンボーン奏者はトランペット奏者に対して地味な印象があるし、トロンボーンはそもそも地味なのではないかと思っていたのだ。
しかし、2月ほど前に出会ってしまったのである。めちゃくちゃカッコイイ楽器に。
それが、このKing 2Bである。とにかく、めちゃくちゃカッコイイ。そして、いかにもカッコイイ音が出そうなのであるから、こりゃ放っておけない。そういえば、ジャズトロンボーンで唯一まともに聴いたことがあるJJ JohnsonもKingを使っていたっけ。ベニーグリーンが何を使っていたのかは存じ上げないが、ああいう、ベニーグリーンのような自由でのびのびとした音楽を奏でる楽器こそ、トロンボーンであり、Kingの楽器なのである。
トランペットすら、まともに吹けないのだけれど、トロンボーンをやると管楽器の基本的な体づくりができそうな気がしている。唇に無理をかけないで、息で音程をコントロールする感覚も身につきそうであるので、それも良い。
とにかく、せっせと練習して、人に尋ねられたら、
「ええ、まあ。嗜むというほどでもないですがトロンボーンを少々」
などと言ってみたいのである。