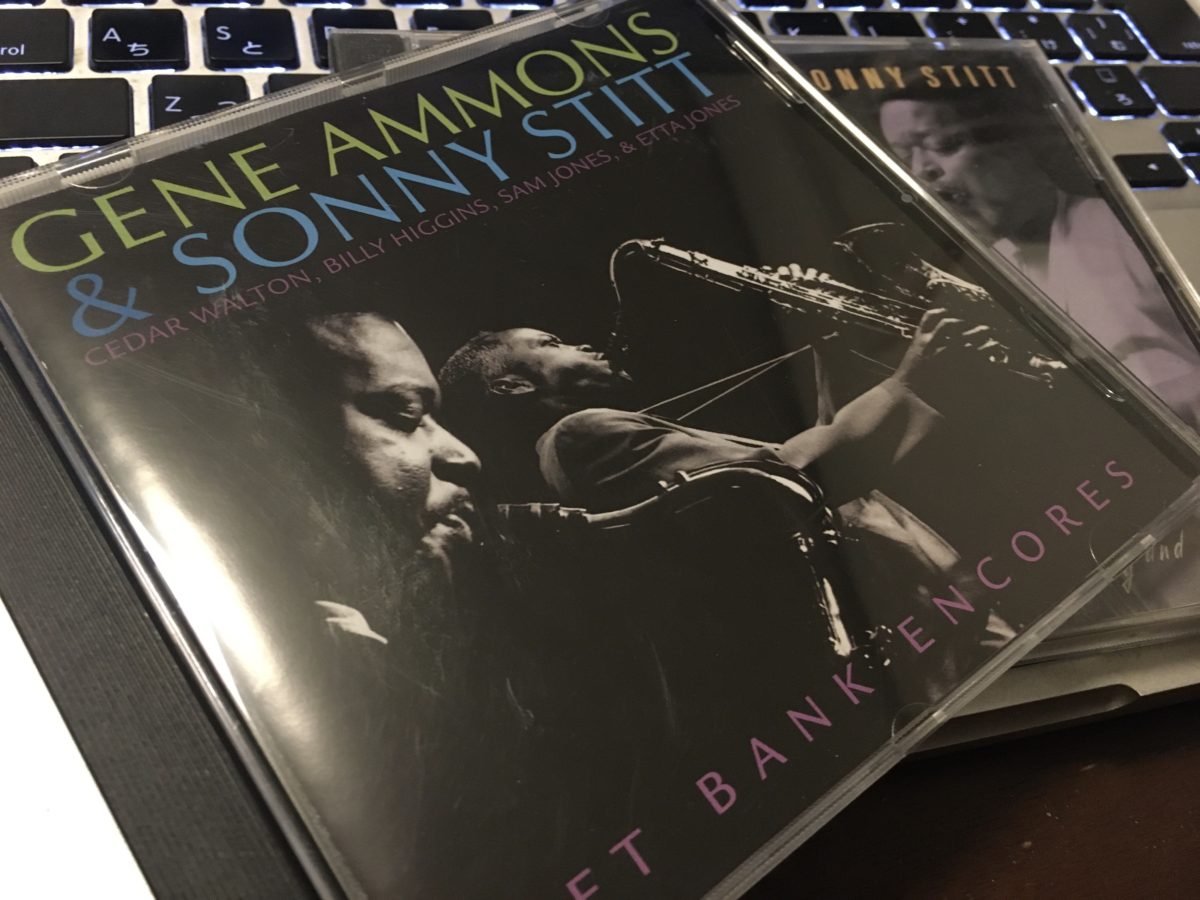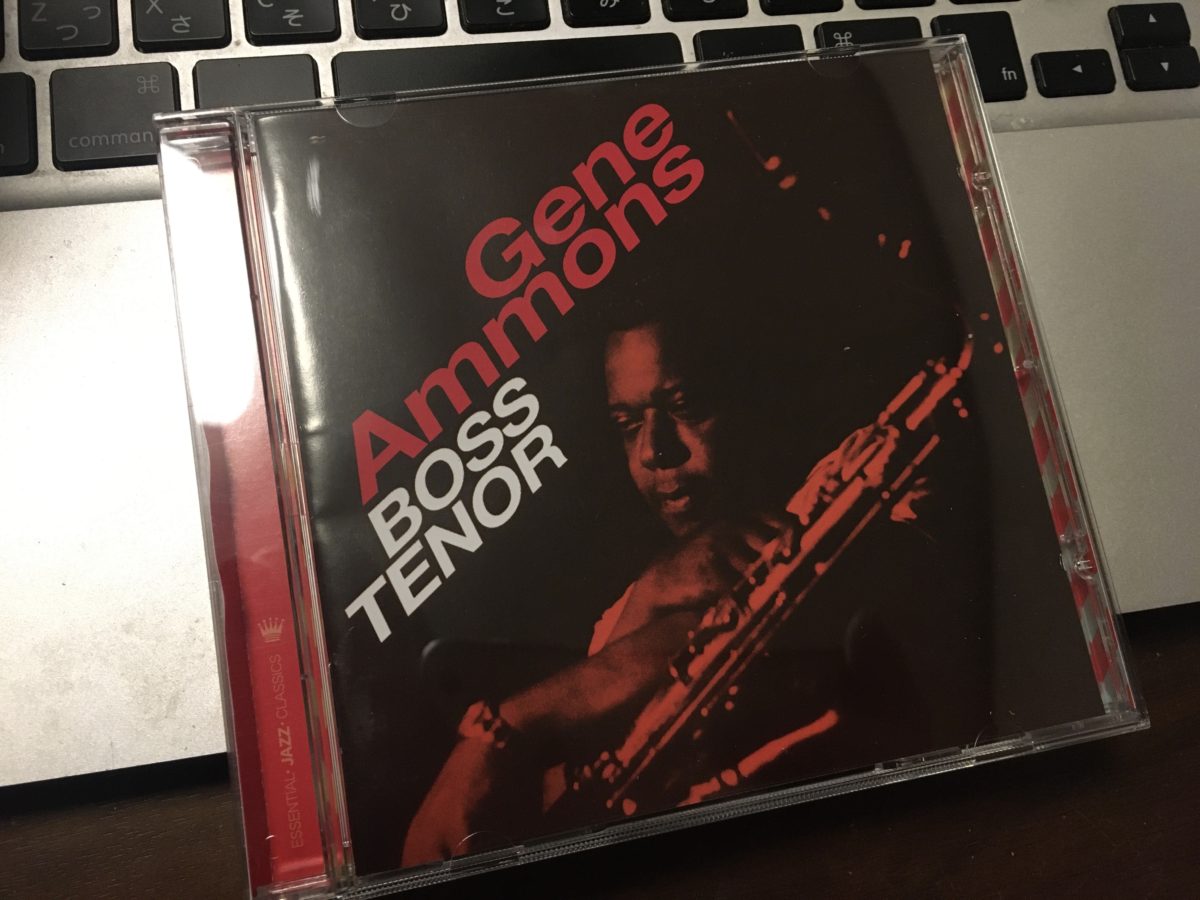私は20代の頃写真が好きだった。好きで好きで、写真家になりたいとすら思っていた。3,000本以上のフィルムを消費し、自分のアパートの部屋に暗室を作り、日夜写真現像にうつつを抜かしていた。
その頃に、金村修さんという写真家のワークショップに出入りし、写真を習っていた。金村先生は難解な言葉を使うことなく、わかりやすく写真を言葉にしてくれた。その言葉を頼りに、バチバチ写真を撮り、ティッシュのように印画紙を消費していた。
それから15年ほど経ち、30代半ばに1年間ぐらいまた写真熱が再燃し、瀬戸正人さんの主宰する「夜の写真学校」に通っていた。瀬戸先生も、なんでも質問したらなんでも答えてくれた。写真は撮った写真を自分で選べるようになるしか上達の手段はない。写真が選べるようになると、自分でどのような写真をとるべきか、撮りたいのかがわかってくる。
上手い写真を撮るというのは、訓練であるが、良い写真を撮るというのは、なかなか訓練ではできない。訓練の上に、引きの強さと、執念がなければならない。ギャンブルに勝つためにはひたすら賭けまくるしかないように、良い写真を撮るためには、ひたすら撮りまくるしかあるまいと思い撮影していた。
近頃は、写真はiPhoneで撮れるようになり、誰もが並の写真家の数倍の量の写真を撮るようになった。だから、もう、写真家の時代は終わったものだと思っていた。それと同時に、私の撮影機材と暗室道具はカビが生えてしまい、ほとんど使われなくなってしまっていた。
そこに、舞い込んできたニュースがあった。東京都写真美術館で瀬戸正人の展覧会が開かれているとのことであった。それを知った翌日、私は瀬戸正人展を見に行った。
瀬戸正人展を見て、すぐに感じたことは、瀬戸正人ぐらいの強力な写真家にとってはiPhoneの脅威はなんのこともないのだと。今の時代、写真を撮り、発表し続けることの厳しさは私の青春時代の2000年代どころではないだろう。
あの頃は、誰もが今のように大量の写真を撮るということはできなかったし、そのような人もいなかった。今は写真を撮るという行為がなんら特別なことではない。だからこそ、写真で何を撮りたいのか、写真がどこに向かっているのかを強く意識して、強くプレゼンテーションしなくてはいけない。そして、強力な写真群を、一貫性を持って見せることができる写真家のみが生き残れる時代になっているのだと思う。
それを考えると、60年代の写真家、ウィノグランド、フリードランダーの写真はすごい。あの時代からそれをやってのけている。結局、写真の本質とはそこだったのだと、今になって思い知らされる。これは当たり前のことではあるけれど、今になって写真とはなんであったのかの定義が再び明らかになろうとしている。
そして、偉大な写真家達は、撮りながらその答えをそれぞれに持っていたのだろう。
私の好きなスデクの写真もそうである。静かでいて、写真に一貫性がある。力強い写真ではないけれど、力強いまとまりがある。そのまとまりがすこしぼんやりしているようにすら見えるのも不思議だ。スデクは、強力な写真家というのとは少しイメージが違う。どちらかというと静かな写真家だ。しかしながら、彼の作品群には、スデクの写真であるということを超えた、写真であることの必然性のようなものがある。
スデクは、写真でみたこの世界を写真というメディアを通して再構築した。当たり前のことをやっているようだけれど、それが、写真で写真を表現するというのはとても難しい。難しい上に根気がいる作業である。それを、生涯を通して、一貫して行なっている。その上、それらの写真群はどれも、陰鬱でありながら清々しい。
瀬戸正人という写真家も、スデクのように、写真というもので写真の世界を再構築しているとも考えることができる。それは、優れた写真家の多くがそうなんだけれど、写真で写真を表現するということの難しさは、私には到底知りえないぐらい途方もない作業だと思う。
きになる方は、ぜひ、瀬戸さんの写真を見てみてください。写真家であるということの途方もないパワーを感じますから。