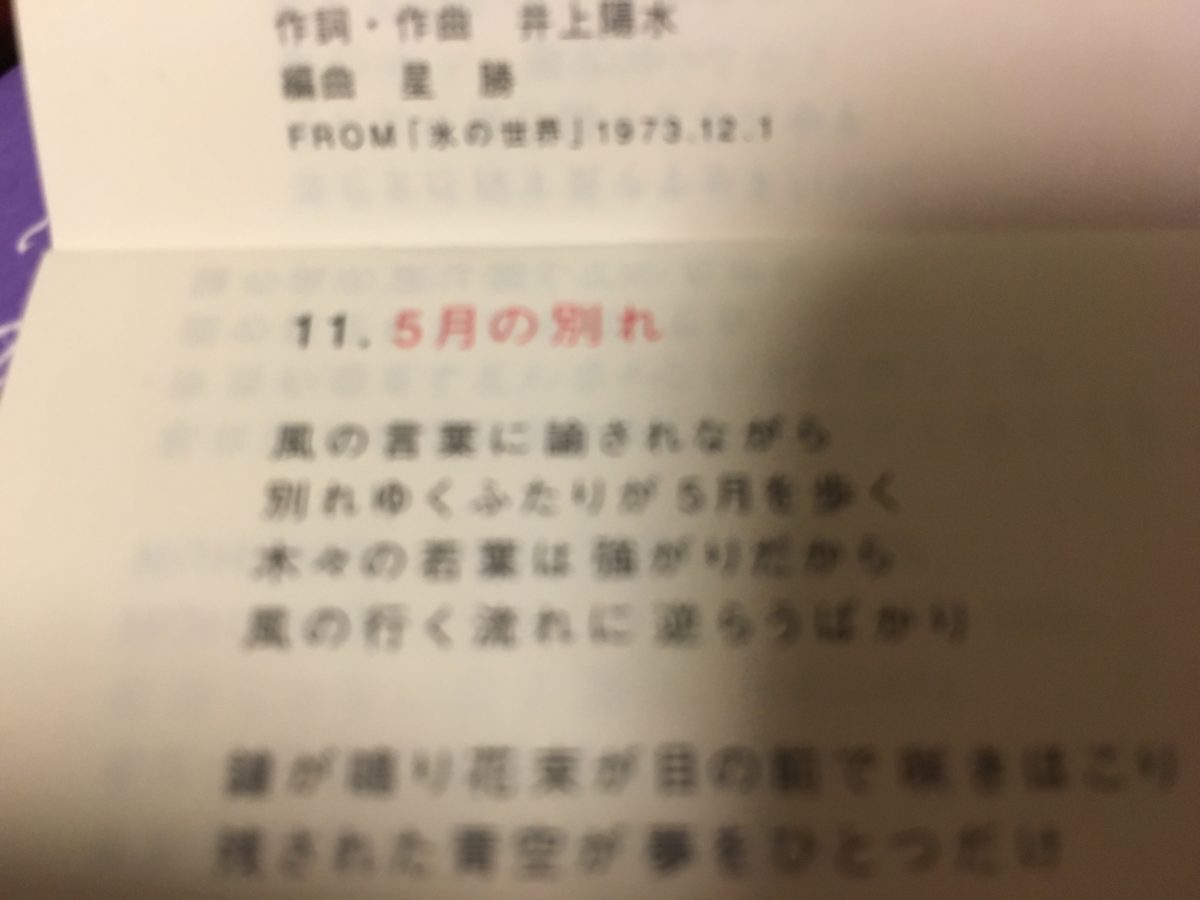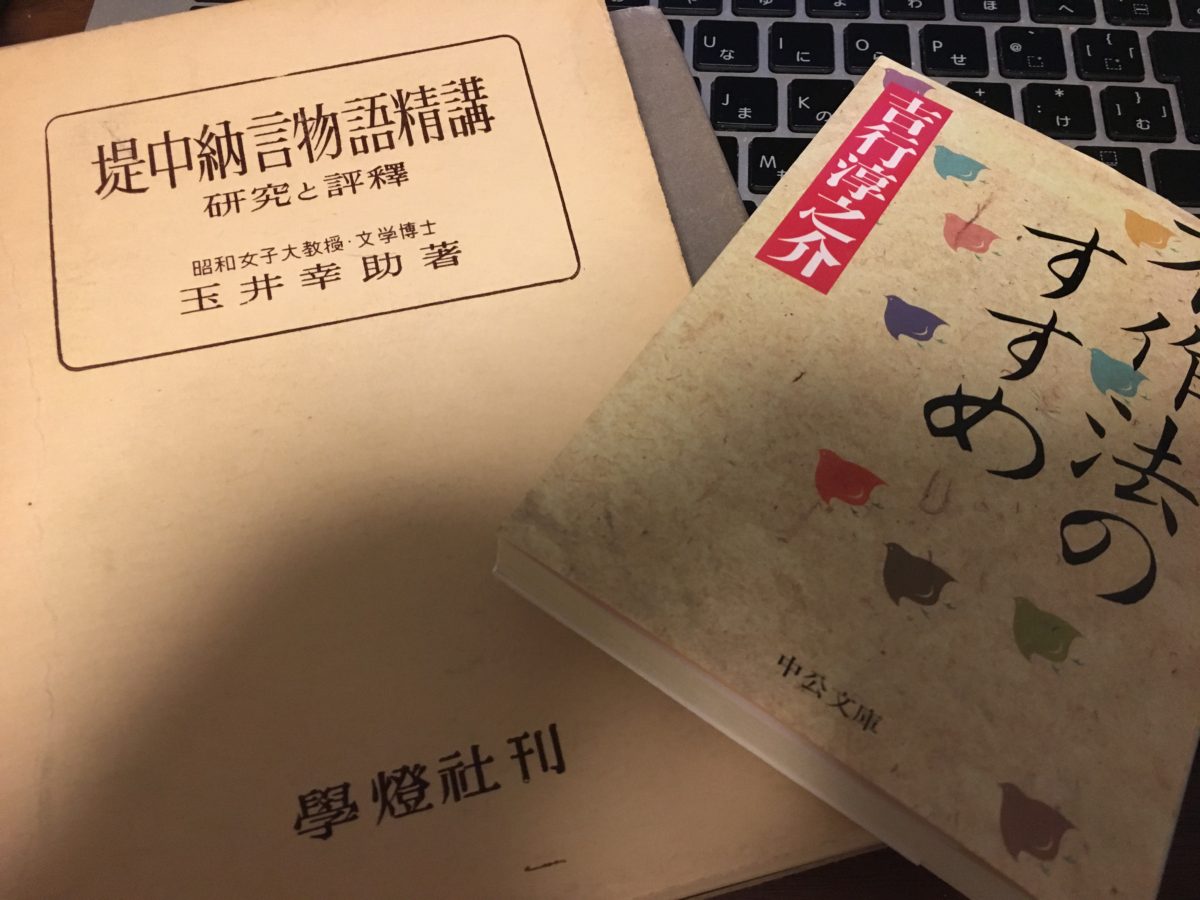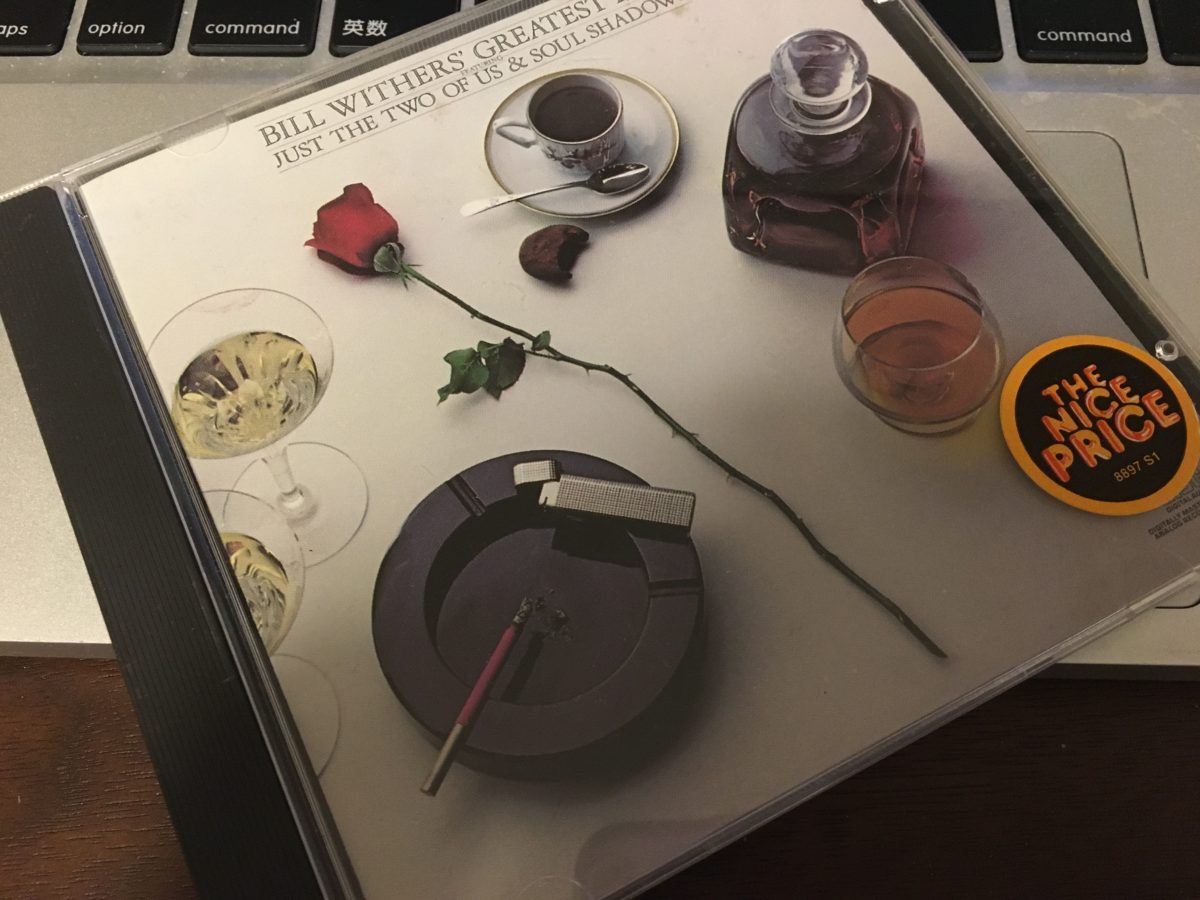チェット・ベーカーは若いころハンサムだったから、なんだか音楽の部分で割り引かれて見られているともう。私が勝手に言うのも失礼だが、損しているともう。若いころのチェットって、あらためて聴いてみると、とても心にしみる音楽をやっている。
人気があったことは確かだし、トランペッターとしての腕も確かだから、当時からそれはそれは高評価されていただろうけれども、これがもっとブサイクな顔をしていたら、聴衆にもっと純粋に音楽を聴いてもられたと思う。ブサイクだったら雑誌の人気投票では上位には入らないかもしれないけれど、それでもやっぱり高く評価されていると思う。
若いころのチェット・ベーカーはなんだか、「いい男」部分が強調されてしまい、アルバムのジャケットなんかがどうも安っぽくなってしまっているような気がする。まあ、中身もそんなに硬派な感じじゃないのだけれど、チェット・ベーカーは硬派じゃないからいいのだ。
歌も、歌えちゃったりするから、どうもそういう軟派なイメージがついてしまっている。音楽自体は40代にヨボヨボになってからの音楽と変わらないのだけれど、若いころはパッケージのせいか、どうもその軟派さに磨きがかかっている。磨きがかかっていて、一見つるつるピカピカしてしまっている。本当は若いころからいぶし銀系の音楽をやっているんだけれど。チェット・ベーカーの若いころのレコードがいぶし銀と評されることはほとんどないんじゃないか。
勿体ない。
例えば、「It could happen to you~Chet Baker Sings」なんて、歌もののレコードなのに、歌が、なんだかナヨナヨしているから、軟派なレコードだと思われがちだ。本職のはずのトランペットのソロもやけに短い。トランペットを吹いていない曲さえある。確かに、これは一聴して軟派なレコードである。
しかしながら、やっている音楽は案外渋い。リズムセクションはやけに豪華で、ノリノリだし、チェットの歌も(スキャットも)ノリノリである。ノリノリでいて、ノリだけで聞かせるのでは無く、ときにしっとり、ときにパリッと聴かせる。
もっと聴きたいと思わせるところまでで抑えられている。「チェットの音楽の魅力を余すところなく聴かせます」という、アルバムではなく、ちょっといいところを匂わせて、指の間から流れ落ちる砂のようにするすると消えて無くなってしまうような音楽だ。この、いいところを匂わせるセンスが素晴らしい。
一曲一曲の収録時間も短いし、聴きやすいのが尚更いい。こんな演奏は各曲10分も聴かせられるような類いの音楽では無く、短めにさらっと聴くのがちょうどいい。そして、収録曲が全曲スタンダードで、曲数も多いので、ジャズの初心者から楽しめる。こういう、ジャズがわたしにはちょうどいい。初めて聴くジャズがこのアルバムだっていう人は、とても羨ましい。それこそジャズの英才教育である。
いきなりローランド・カークから聴き始めても構わんのだが。