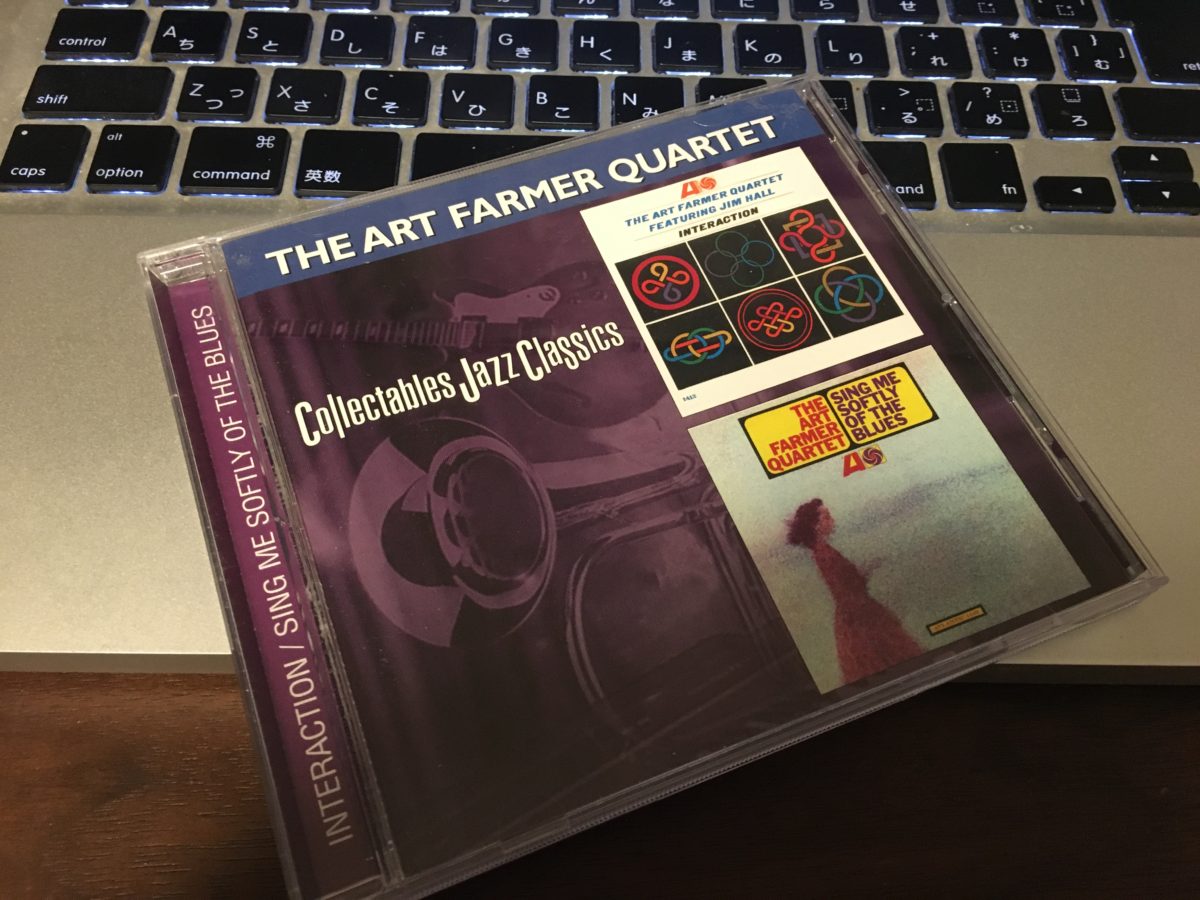学生の頃は時々ジャズのライブを聴きに行った。
今はビルボード東京だとかCotton Clubとか、いろいろと大物が出るジャズクラブがあるけれど、私が学生の頃はまだそういう店はなかったんじゃないか。いや、あったかもしれないけれど、行ったことがなかった。ブルーノート東京に何度か行ったことがあるくらい。それも、高いから、学生券で聴いたような気がする。
そもそも、学生時代を国立で過ごした私は、東京の西側(多摩地区)からほとんど出ることがなかった。いつも、国分寺のT’sという友人がマスターをやっていた店に行ったりしていた。新宿まで出て行くのも2月に一度くらい。普段なら足を伸ばしても吉祥寺ぐらいが関の山だった。
吉祥寺にサムタイムというジャズバーがあって、今もあるんだろうけれど、そこにはよく行った。月に一度ぐらいは行っていた。サムタイムで五十嵐一生のカルテットやらを聴きに行っていた。当時はジャズ研でトランペットを吹こうと思っていたので、ジャズのライブもトランペットものばかりを聴きに行っていた。五十嵐一生、日野皓正、高瀬龍一、松島啓二を何度か聴きに行った。トランペット以外のライブはあまり聴きに行かなかった。川嶋哲郎をなんどか聴いたけれど、それぐらいか。
サムタイムはいつもスケジュールをろくすっぽ確認しないでふらりと行った。チャージが1,500円と安かったことと、お酒も安かったことも手伝い、学生でも入りやすい店だった。今はいくらになっているのかわからないけれど、とにかく、安くライブが聴けてふらりと入れる貴重なジャズバーだった。
今日、御茶ノ水のディスクユニオンに行ってバーニーケッセルのCDを見ていたら、Barney Kessel “Live at Sometime”というCDがあった。そういうCDがあるということはジャズ研の後輩に聞いていたのだけれど、現物を見たのはこれが初めてだ。ジャケットを見ると、なんとも懐かしいサムタイムの店の壁の前のテーブルにバーニーケッセルが腰かけている写真で、ついつい買ってしまった。
家に帰ってCDプレーヤーでかけてみると、これが案外録音も悪くない。それに、バーニーケッセルだ。間違いない演奏である。あの、なつかしい吉祥寺の店で、バーニーケッセルがライブをやったと思うと、感慨深いものがある。
バーニーケッセルの演奏は、期待通りでリラックスしていて良い。コード弾きでメロディーラインをなぞっていく感じとか、単音で弾くソロも、なんとも渋くて良い。
バーニーケッセルのギターは、サムタイムぐらいの広さの店で聴くのが一番合っているような気分になる。スタジアムやら、野外会場で聴くよりもすこし小さめのハコで、ゆっくりウィスキーでも傾けながら、真剣にならずに聴いていると、この音楽の良さが体に染み渡ってくると思う。
また近いうちにサムタイムに行ってみようかな。