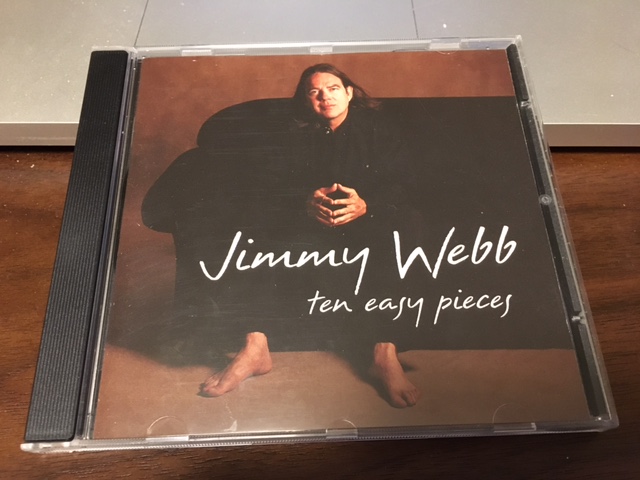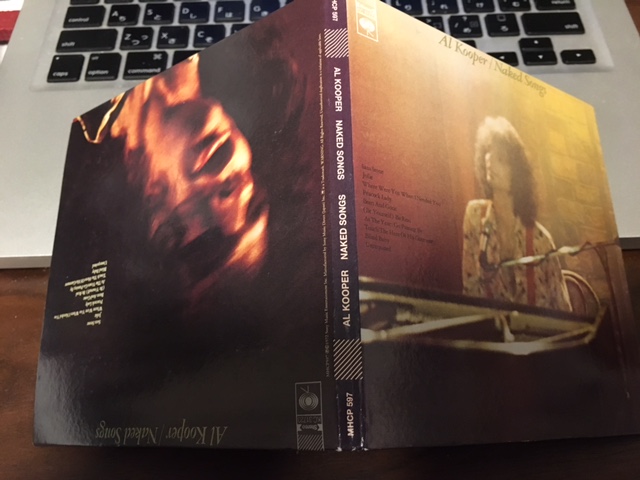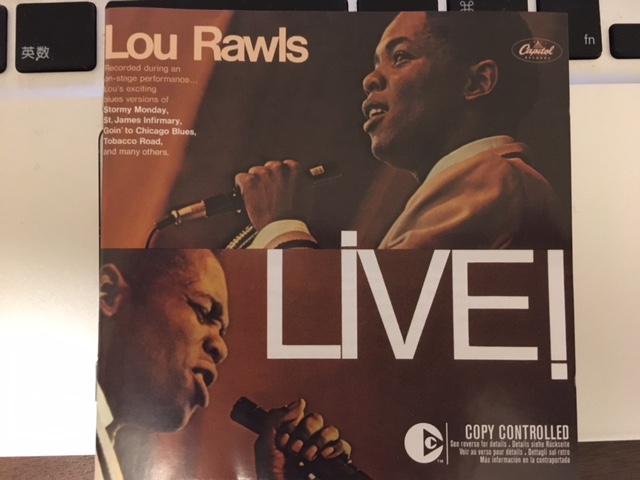昨日は Carole Kingの「The Living Room Tour」というライブアルバムを聴いていて、あまりにも圧倒されてしまい、ブログを更新できなかった。全ての曲が心地よく、リラックスしているのに、力強く心に残る。キャロルキングって優れたソングライターであると同時にものすごいシンガーなんだなぁ、とあらためて感心した。
この「The Living Room Tour」は先日ふと読んだブログで紹介されていたのだが、そこでもこのライブアルバムのリラックスしていてアットホームな雰囲気が素晴らしいと書かれていた。その通りだった。シンプルなピアノやギターの伴奏で歌われる曲の数々が、リラックスしているといっても、程よい緊張感を持ちながらイキイキしている。こんなライブができるキャロルキングってすごい。
このアルバムは2005年に録音されているのだが、その時点でキャロルキングは62歳(と彼女は歌の中で言っている)らしい。彼女の長いキャリアの中でたくさんある名曲がこのアルバムではじっくり聴ける。
もちろん、このアルバムに入っていない曲でも、このリラックスした雰囲気で聴きたい曲はたくさんあるけれど、それでも、全部聴いてしまうとお腹いっぱいになるから、このぐらいのボリュームがちょうどいいのかもしれない。2枚組だから、実際のところ結構長いアルバムなのだけれど、するっと聴きとおせた。
アルバムの音楽そのものから話は変わるけれど、このCDを聴いていて気づいたことなのだが、ピエゾピックアップのエレアコの音って、2005年からあんまり変わっていないんだな。
特に低音弦の音は10年以上経った今もこの当時と同じくツブツブした音がする。アコースティックギターの生の低音弦の音のような隙間のある太い音ではなくて、なんだか人工的な倍音が強調された音がする。
結局この頃から10年以上が経って今でもこの音でエレアコの音が定着しているっていうことは、こういう音がギター弾きの中でギターの音として浸透したということなんだろうな。こういう「ピエゾの音」っていう音がギターの音色の一つとして確立されたということなんだろうな。
もっとも、今はピエゾ以外のピックアップがエレアコのピックアップの選択肢としてたくさん出ている。マグネティックのピックアップも進化したし、コンデンサーマイクだとかL.R Baggs、FISHMANをはじめとしていろいろ新しいシステムを作っている。
そういうピックアップの選択により、エレキギターに近いサウンドも出せるし、もっと生のアコースティックギターに近い音も出せる。2005年当時よりも今の方がきっとずっとアコースティックギター用のピックアップの音は多様化している。
けれども、このピエゾピックアップのツブツブした音は変わらずに生き続けている。ピエゾピックアップは結構古いから(一般的には70年代から使われている)40年以上の歴史がある。その間にこの音が定着したのだろう。
私もピエゾのギターを持っているけれども、あまり使わないので今は人に借している。けれど、時々ピエゾのギターを弾くとそのコンプレッションのかかった音の気持ち良さもわかる気がする。弾いていてなんだかちょっと気分がいい。きっとピエゾの音は聞き手(リスナー)に浸透する前に弾き手(プレーヤー)にウケけたんだろう。新しいギターの音として。
キャロルキングの凄いアルバムを聴いて、こういうどうでもいいことを考えてしまった。
アルバム自体は、すごくオススメです。