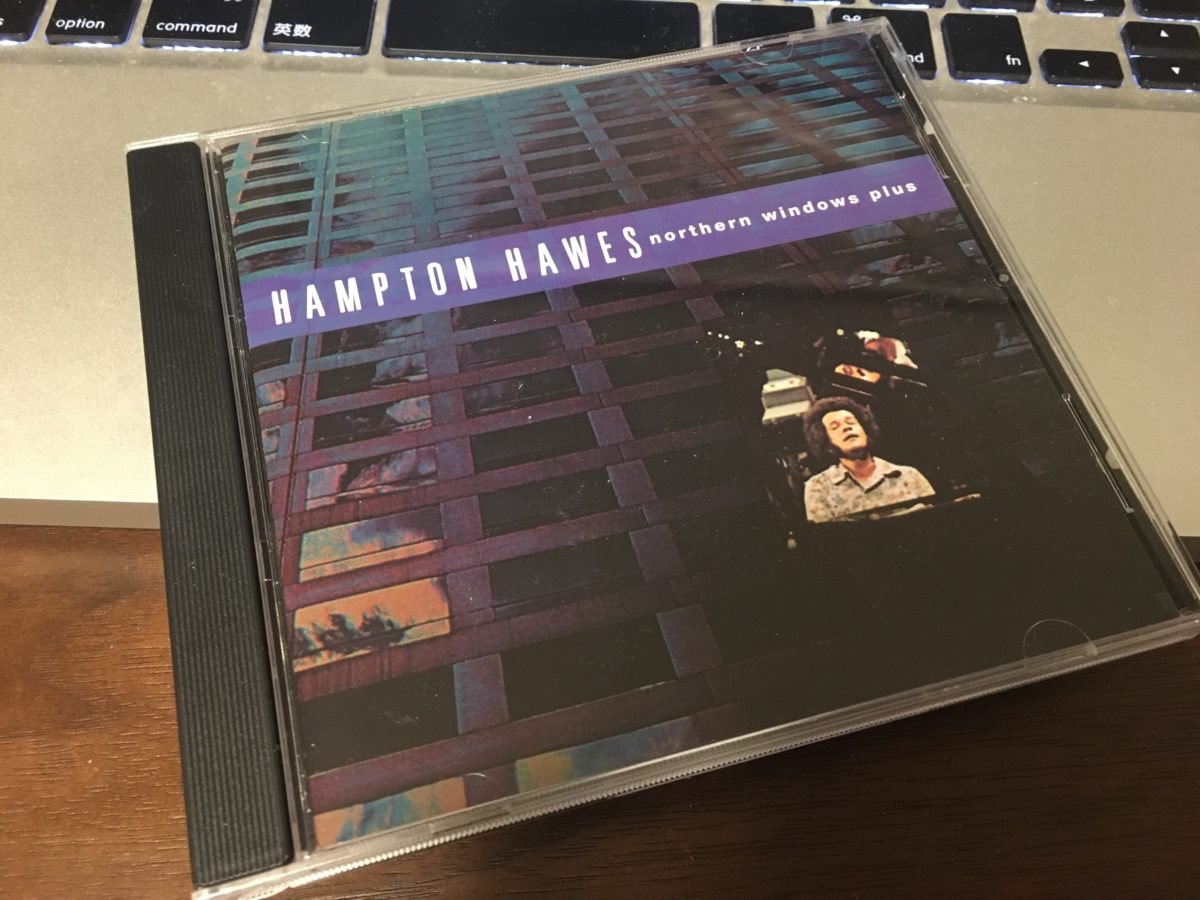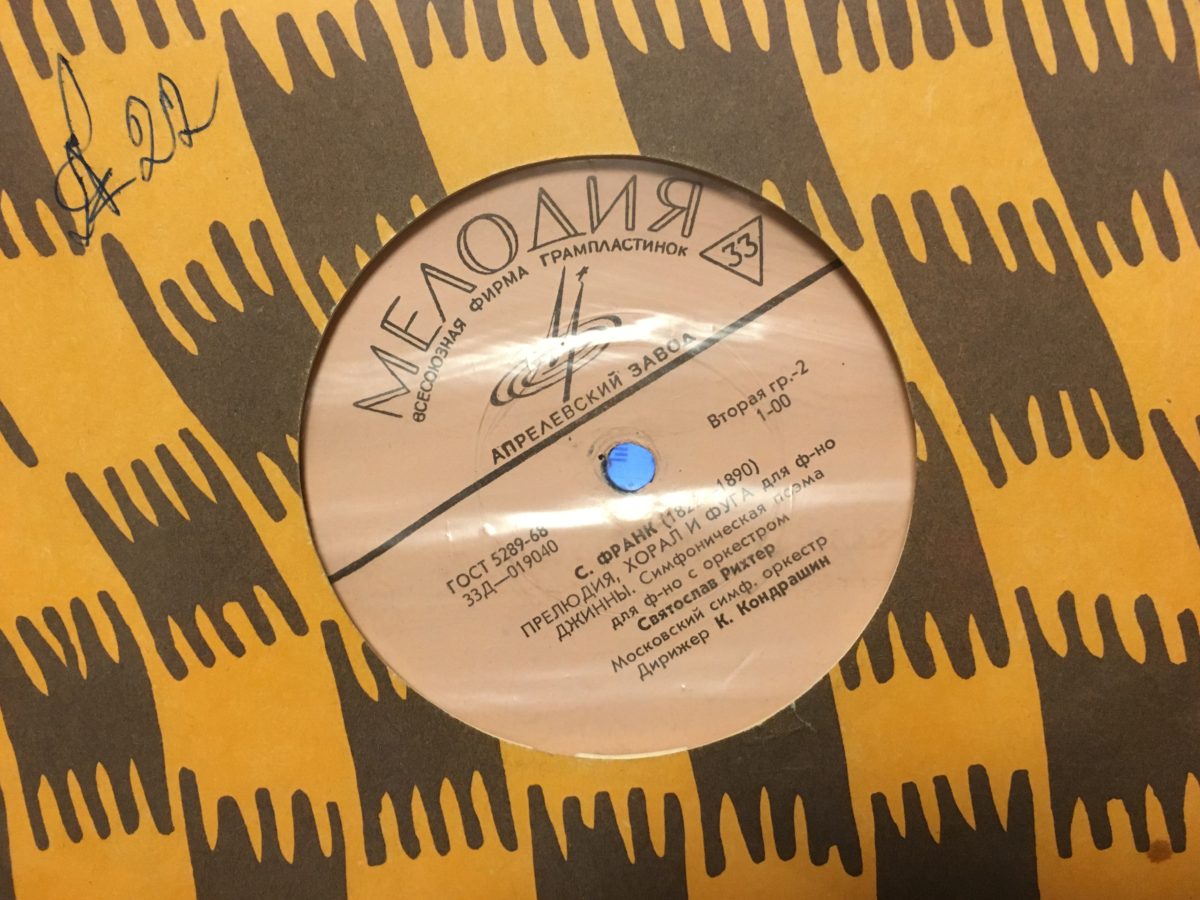Red Garlandのまだ聴いていなかった名盤があった。”The Nearness of You”というタイトルのバラード集。
ジャズのアルバムで、ピアノトリオで、バラード集というのは結構たくさん出ていて、物によっては単なるラウンジミュージックになってしまっていたり、逆に難解な解釈になっていたりして聴きづらかったりするのだけれど、このレッド・ガーランドのアルバムは、シンプルでいてなかなか聴きごたえのあるアルバムに仕上がっている。とは言っても、聴いていて疲れるようなアルバムではなく、甘ったるくなりすぎないで、純粋にレッド・ガーランドのピアノトリオの無駄のないアンサンブルを堪能できる。
私は、あまりジャズのピアノトリオのアルバムを持っていない。普段あまりピアノトリオを聴こうと思わないからだ。だいたいいつもは、オルガントリオ(オルガン、ギター、ドラムス)編成のアルバムか、管楽器が入っているアルバム、それもワンホーンカルテットが好きで、よく聴いている。トランペット、テナーがフロントのクインテットのアルバムも結構沢山持っていて、とくにマイルスの50年代のクインテットやら、チェットベーカーの65年あたりのクインテットなんかは好きで時々聴くのだけれども、どちらかというとワンホーンの方が好きだ。
オルガントリオの魅力については、別のところに書くとしよう。
ワンホーンカルテット、特にトランペットがフロントのをよく聴いているんだけれど、何故好きかというと、トランペットの魅力というのを一番堪能できるからだ。トランペッターの力量、歌心が一番試されるのはそういう編成だと思っている。フロント楽器のハーモニーで聴かせるジャズよりも、歌モノに近い。ワンホーンカルテットでは、フロント楽器があまり暴れてしまうと、まとまりがつかなくなってしまう。だから、ワンホーンの編成では、テクニックをひけらかしたり、ハイノートをヒットしまくる音楽よりも、じっくり歌を聴かせるアルバムが多い。そいういうアルバムの方が聴いていて疲れないし、じっくり何度でも聞くに耐えうる。だから好きなんだろう。
ピアノトリオは、いろいろなスタイルを実験できうる編成であると思う。キース・ジャレットのスタンダードトリオのように、トリオでいかに自由に音楽を料理できるかを試す実験の現場にもできるし、ビル・エバンストリオのように、ピアノという楽器の表現の可能性を最大限に発揮することもできるし、はたまた上記のようにラウンジミュージックにもできる。だから、ちょっとした味付けの違いでいろいろな音楽に転んでしまうし、聴く方としては、それを楽しむことができる。
レッド・ガーランドトリオは、常に安定している。ベースやドラムスは色々と入れ替わったりすることはあるけれども。サウンドは常に変わらない。だから、彼のトリオのアルバムは、だいたいハズレはない。ハズレはないけれども、ものすごく実験的なことなんかは、絶対に期待できない。スイングしまくるし、ジャズという音楽のある意味完成形ではあるのだけれども、あまりにも安定しすぎていて、刺激がないのであまり好きになれないという方もいるだろう。この人は「時々アバンギャルドなことをやる」というようなタイプでもない。冷静沈着で、自分のスタイルを生涯貫いた。新しいスタイルを創り上げたパイオニアとも言えないだろう。むしろ、彼は彼のスタイルでの最高の名手だ。
ブロックコードを基調として、テーマもソロもとる。早弾きはほとんどない。だけれども、ものすごく、聴いていてウキウキするし、時にしっとりとまとめ上げる。彼のように弾けるというピアニストは、他にもいるだろう。オスカーピーターソンなんかは、彼のスタイルを踏襲し、もっとテクニックを駆使し、複雑なこともやってのける。だけど、彼は、あえて彼のスタイルを変えることなく、ピアノを弾き続けた。音楽の魅力って、いや、ミュージシャンの魅力っていうのはそこが重要なんだと思う。
これは、音楽に限ったことではないと思う。私個人の趣味といえばそれまでなんだろうけれど、表現とは「なにができるか」ではなく「なにをやらないか」が重要なんだと思う。そして、それは「なにしかできない」ということでも構わないと思う。その道である程度の水準(とは言ってもかなり高度なレベルにおいてだけれど)をクリアしていれば、このミュージシャン(作家でもいい)は「これができない」から劣っているということは基本的にはないと思う。むしろ、「この人はこれ以外できない」というのこそ、魅力になり得る。「〜節」という言葉があるけれど、それは、ちょっと狭い意味であって、もっとおおらかな次元において「これ以外できない」ということは、とても魅力的なことであると思う。
誤解がないように言っておくと「テクニックが劣っている方が素晴らしい」ということを言っているわけではない。むしろ、ディジーガレスピーやらパコ・デ・ルシアのようにテクニックが優れていようと、一つの道を極め、そればかり突き詰めるというタイプのミュージシャンにこそ魅力があるのだ。ディジーガレスピーはモーダルなジャズやフュージョンもやっているのかもしれないけれども、彼の音楽の魅力は最後まで50年代初頭までのスタイルのジャズを生涯貫いていいたからであり、そのためディジーは常に期待通りのことを軽々とやってのけるからである。
レッド・ガーランドのそういう魅力は、このバラード集でも存分に発揮されている。レッド・ガーランドのレコードに期待していることの総てがこの一枚に詰まっている。私は、彼のレコードを買って、そのバリエーションを楽しむことに喜びを憶える。そして、レッド・ガーランドはつねにそこにいてくれる。