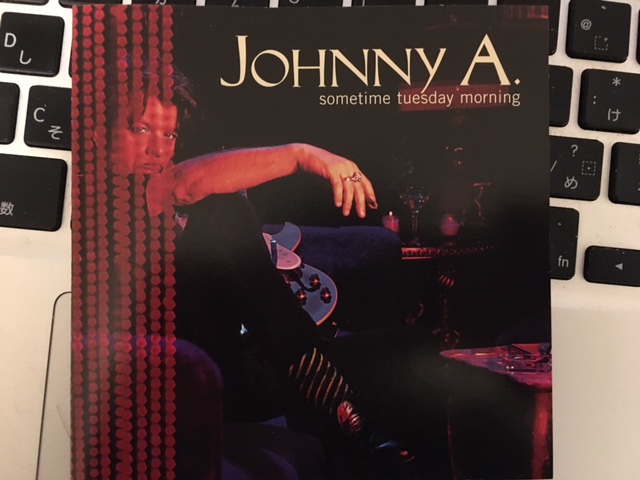音楽というものを何も聴く気が起きなくなった。
半年ほど前から体調を崩してしまい、それ以来音楽を聴くのすら辛いことがある。まあ、そんな命に関わるような病気じゃないからいいのだけれど。
ちょっとカントリーのアルバムでも聴こうと思ったのだが、CDプレーヤーのトレイを開けただけで聴く気が失せてしまった。
しかし、何も音楽を聴かないでいると何となく落ち着かない。こういう時はあまり刺激のない音楽を聴きたい。いや、本当は何も聞かないほうがいいのかもしれないけれど。
No Music, No Lifeとタワーレコードが叫んでいたけれども、実際のところ音楽を聞かなくてもなんとか生きていくことはできる。ただ、退屈なだけである。退屈とは、私にとってとてもストレスであることは確かなようだ。入院していた時など、持ち込める音楽のプレーヤーなんかに制限があって、結局ひと月ぐらい何も聞かないで過ごした。退屈であった。自分でも思っていたよりもストレスが溜まっていたようだ。外泊で自宅に戻った際に音楽を聴こうとCDラックに飛びつくように聴きたい音楽を探し、聴いたが、結局疲れてしまい、あんなに聴きたかった音楽もろくに聴けなかった。
退院してみて、少し気分に余裕が出てきて、まあ、そんなに焦って音楽を聴かなくたっていいと思えるようになった。それで、力が少し抜けて、音楽を聴いていても疲れなくなってきた。
しかし、今夜は音楽が聴きたいのに、聴く気力が起きないという事態にまた陥ってしまった。何か聴きたいのだが、どれもいざ聴こうと思うと聴く前から疲れてしまうのだ。
そうしているうちに、何となくCDラックの一番上に平積みになっていた大貫妙子のベスト盤が目に入ったのだ。
これなら、何となく聴けそうだ
そう思い、CDプレーヤーに入れてかけてみた。思った通り、音楽がすんなり耳に流れ込んできた。こういう気力が湧かない最低な時に大貫妙子さんの音楽はよく合うな。まるでミミを切り落とした食パンにハムとマヨネーズがよく合うかのように合うな、なんておかしなことまで考えてしまった。
きっと彼女の声がいいんだろうな。少女のようで母のような歌声。まあ、私の母ちゃんはこんな声じゃないけれど。
彼女の2枚組のベスト盤「大貫妙子 ライブラリー」の2枚目を聴いているのだが、どの曲も独特の爽やかさと、凛とした感じ、ちょっと儚さを感じさせる優しさがいいな。彼女の音楽を言葉で表せるような語彙を私は持っていないんだな。だからいいのかもしれない。言葉にしてしまったら、こういう気分の時にその言葉が壁になってしまい音楽を受け止めるのにパワーが必要になってしまう。彼女の音楽と私の間にはそういう壁がないんだな。
メロディーもそうだけど、歌い方がとっても素朴で、純粋な感じがするから、簡単なんじゃないかと思って、自分でも弾き語りできるんじゃないかと、ちょっとコード譜を見て歌おうとしたことあったけれど、すごくコードが難しくて歌えなかった。
中でも、京成スカイライナーのCMソングになった「はるかな HOME TOWN」っていう曲が好きだ。八木伸郎のハーモニカがとても心地いい。ハーモニカってこんなに澄んだ音色が出るんだな。まるでパイプの先から静かに立ち昇る煙のような音色だな。
一度、八木のぶおさんのハーモニカを生で聴いたことがある。池袋のジャズフェスティバルに出演していたビッグバンドのゲスト奏者として2曲吹いていた。池袋の駅前の公園に設置された野外ステージでの演奏だった。
日が沈んできて、ちょうど夕焼けが綺麗に赤く焼け始めた時に、八木のぶおさんはクロマチックハーモニカからブルースハープに持ち替えてソロを吹いた。その時、池袋駅前の空気がパーっと夕空の色と一緒になったような気がした。ブルースハープの音の響きが、一度も訪れたことのない童謡の中の「故郷」に私たちを連れて行ってくれたような感覚すら憶えた。20代の頃、高校時代からの友人と二人で聴いたのだった。とても心地のいい音楽だった。