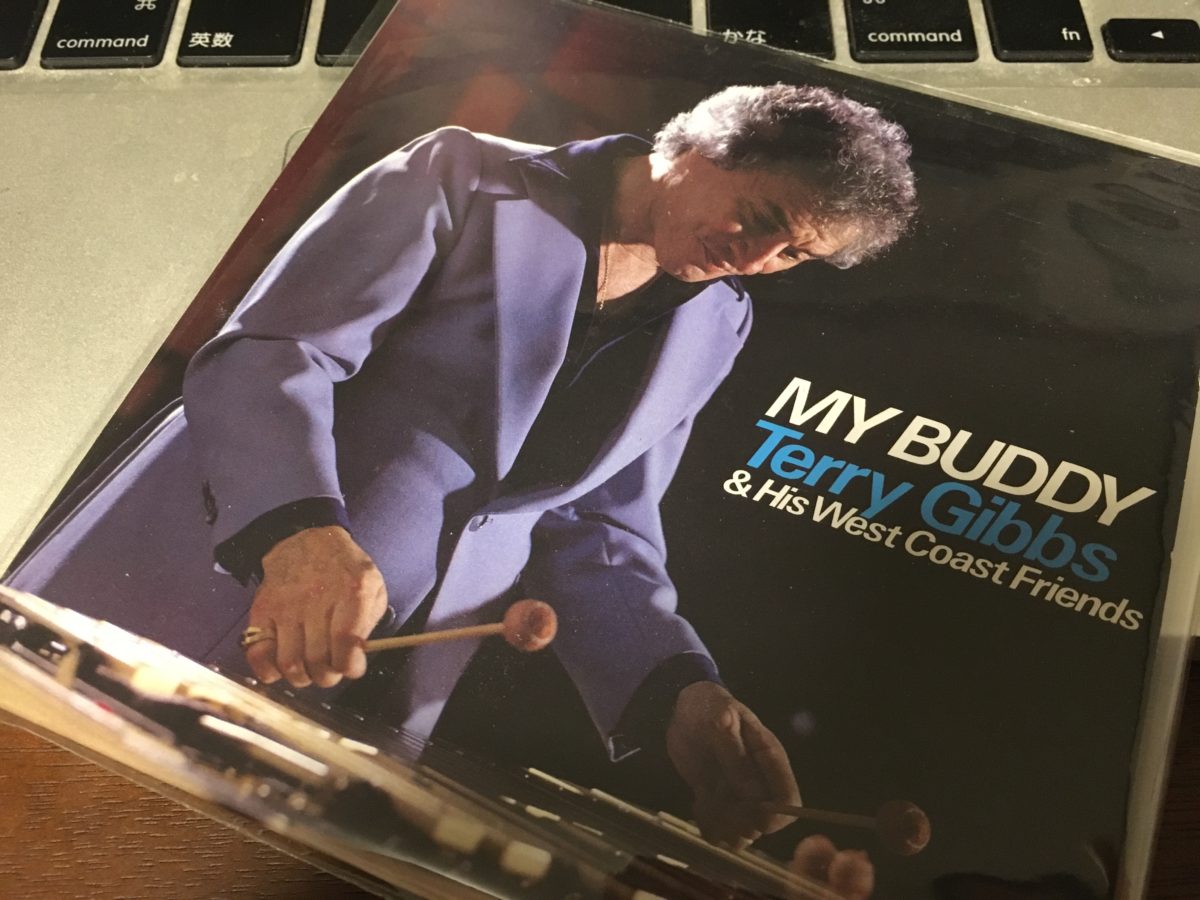私はその頃、毎晩のように大学のゼミの後輩の女の子が住む寮の部屋に居座っていた。
私は、大学を2年も留年してしまっていて、大学6年生の夏を迎えていた。5年間付き添ってきた私の交際相手は、清く正しく4年生で卒業し、卒業したのちも1年間は勉強と私との時間を過ごすために東京に残っていてくれたのだが、一年が経過したところで、九州の実家に帰ってしまっていた。
独り東京に取り残された私は、誰とつるむこともできず、寂しい毎日を送っていた。それまでは、毎日朝から晩まで一緒にいてくれた交際相手を失ってしまったことで心が空っぽになりそうになっていた。本当に空っぽになっていたわけではないが、写真の撮影と現像を繰り返す毎日にも虚しいものを感じていた。大学の授業には参加せず、独り部屋にこもったり、街へ出て街行く人々を写真に収めていた。
そんな中で、親しくなったのは、大学でのアクティビティーのうち唯一参加していたゼミナールのメンバーの女の子だった。彼女の大学のゼミでの研究テーマは文学とセックスについてだった。そのせいもあり、彼女は性に開放的で、ゼミナールのメンバーと酒を呑みに行った際も、開けっぴろげに性についての論議をぶちかましていた。
そんな彼女と親しくなったのは、大学6年生の夏のことだった。
大学の夏学期の終わりのテスト期間を控えた頃、講義には出ていなかった私は、単位取得のためのテスト勉強のストレスもあり、たびたびゼミナールのメンバー数人で居酒屋で夜遅くまで激論を交わしていた。
そんなある夜、結局居酒屋も閉店の時間まで飲んでしまい、やるかたなしに私たち数名は彼女の寮の部屋に転がり込んだ。私を含めた男3名が、女子寮の部屋にころがりこめたということも、今となっては不思議なのであるが、彼女の部屋に缶チューハイやワインを持ち込み朝方まで話し込んだり、中平卓馬のビデオを鑑賞したりしていた。
夜も更けて、朝方になりだすと、私以外の男連中は彼女の部屋の中の想い想いの所に横になった。酒の酔いが覚めてしまった私と、彼女は、二人彼女のベッドに横たわりながら眠ることもできず明けていく朝日を眺めていた。もちろん、着衣のままなので、いかがわしいことはなかったが、時折体が触れ合うと、当時25歳だった私は、何とも気まずい思いをしたことを覚えている。朝日を見ていることしかすることがなかった私たちは、仕方がないので、そのまま抱き合い、ささやき声で世の中の不合理について話を始めた。
彼女にはイギリスに住むイギリス人の交際相手がいるということだったが、なかなか会いに行けるわけでもないし、退屈と孤独を持て余しているということだった。折良く、私も似たような境遇であったので、私たち二人は馬があった。その孤独を補うために、私たち二人は着衣のまま抱き合い、いつしか眠りに落ちた。
その翌日から、私は独り毎晩彼女の部屋を訪れるようになった。6月の終わりだった。私たち二人は、特に言葉をかわすこともなく当然のように同居し、部屋のテレビを見ながら、毎晩遅くまで呑んでいた。一通り飲んでしまうと、私たち二人は、彼女のシングルのベッドに横たわり、そのまま眠りに落ちた。
なぜだか、そういう生活が当たり前のように感じていた。夕方に居酒屋か彼女の部屋で落ち合い、彼女がイギリス人の彼氏と電話をする横で私はテレビを見て、缶チューハイを飲んだ。電話が終わると、彼女は私の横にぴったりと腰掛け、缶チューハイを空けた。
そんな生活が、3週間ぐらい続いただろうか。テスト期間も終盤に差し掛かり、東京の夜は暑くなり、お互いに気兼ねしなくなった私たちは下着になって、毎晩抱き合い眠りに落ちた。彼女とはそれ以上の関係を持ったことはなかったが、それは、性に開放的でアグレッシブな彼女に気後れして、そういった行為が苦手な私のほうがそういう事態になることを意図的に避けていたのかもしれない。
最後のテストが終わった雨の晩、私は、お祝いに花屋で買ってきた小さな花束と、缶チューハイ数本とシャブリのボトルを持って、彼女の部屋に戻った。その夜も同じように私たちは下着姿で抱き合って眠りに落ちた。
朝起きてみると、空は快晴で、朝日が眩しかった。まだ寝息を立てている彼女の横で私はピースライトに火をつけ、朝を眺めていた。
朝の8時頃まで彼女は眠っていただろうか。寮の裏のグラウンドから、野球のれんしゅうの音が聞こえてきていた。私は彼女の肩をゆさぶり、
「おい、夏休みが来たぞ! 起きて、何かを食べに行こうよ」と声をかけた。彼女はやっと起床し、服を着て、私のピースに火をつけ2〜3腹吸ったのち、灰皿にのこちのタバコを押し付けて、
「よし、カレーを食べにいくぞ」
と私に宣言して寮の近くの欧州カレー専門店に私を連れ出した。
みせの席に座った際、私はかのじょの部屋にピースの箱を置いてきたことをわすれた。彼女はさぞ当然のように、少し離れたタバコ屋まで、私にタバコを買わせに行かせた。
カレー屋に戻り、ピースに火をつけて、彼女にも一本差し出すと、彼女は遠慮なくその一本を吸い始めた。
「これ、ずいぶんきついタバコね。それにタバコの葉派が口に残るでしょう?私には、もう少し軽いやつを買ってきてちょうだい。」
と頼むので、近くのコンビニまで走り、彼女になんのタバコだったかは忘れたけれど、5ミリぐらいのタバコを買ってきた。
カレー屋には私たち二人と、ゲイのマスターとアルバイトしかいなかった。マスターとアルバイトはなんだか楽しそうに話していた。食べ終えた私たちはなんの気兼ねもなくいつまでも話し込んだ。
結局、彼女は私が買ってきた5ミリのタバコを吸うことなく、私のショートピースをふかした。二人で一本のピースを、いつまでも吸い続けた。ゼミナールのメンバーの噂話や、その時好きだったウディアレンの映画なんかについて話し合いながら。
ショートピースの箱がなくなり、私たちは店の前で別れた。
その日は、彼女のイギリスのボーイフレンドが彼女に会いにくる日だった。彼が成田に着くのは私たちがカレー屋を出た頃だった。
私は、また独りになり、到来した夏休みをどのように過ごすべきか考えていた。また函館に一週間ほど旅行に行こうか。それとも京都に行こうか。その両方ができなかった。ゼミナールの彼女と過ごした時間の残り香が、私についていたから、それはできなかった。その代わり、私の交際相手が九州から私に会いに来てくれた。それは、偶然のことではなく、もうかれこれひと月前から予定されていたことだった。
彼女が東京に来るまでどのように過ごすか、それが私に課された問題だった。私は、一番簡単な答え、昼寝をして夕刻から酒を飲みに行くことを選んだ。だから、その日、家に帰って昼寝をして、夕方を待ちいつも通っていた「とむ」という居酒屋で酒を飲んだ。ひとりで飲むのはあまりにも辛かったので、所属していたサークルの後輩と二人で飲んだ。
酒に弱い私も、その日だけはなぜだか酔うことができなく、7時には店を出た。店を出て、まっすぐ家に帰れば良いものを、私とサークルの後輩は二人で、ゼミナールの彼女の住む寮の方向へ続く道を歩いた。その夜、道の脇の空き地ではすこし早い盆踊りが行われていた。私たち二人はその盆踊りで生ビールを買い、なんとなしに飲みながら、盆踊りの輪を眺めていた。
ふと、その輪の中にゼミナールの彼女の姿があった、彼女の横には似合わない浴衣を着たボーイフレンドの姿もあった。二人を眺めていた私を彼女が見とめ、こちらに歩いてきた。ボーイフレンドと二人で。
彼女は、私にボーイフレンドを紹介した。彼はイギリス英語で私に話しかけてきた。極めて紳士的に。
「君がいつも世話になっているリョーか、面倒をかけてるみたいだね」
「いえ、めんどうをかけているのはこちらの方です」
そのまま、わたしたち4人は盛り上がり、盆踊りの輪に入り、最後の曲が終わるまでビールを飲みながら踊った。
夏の始まりだった。