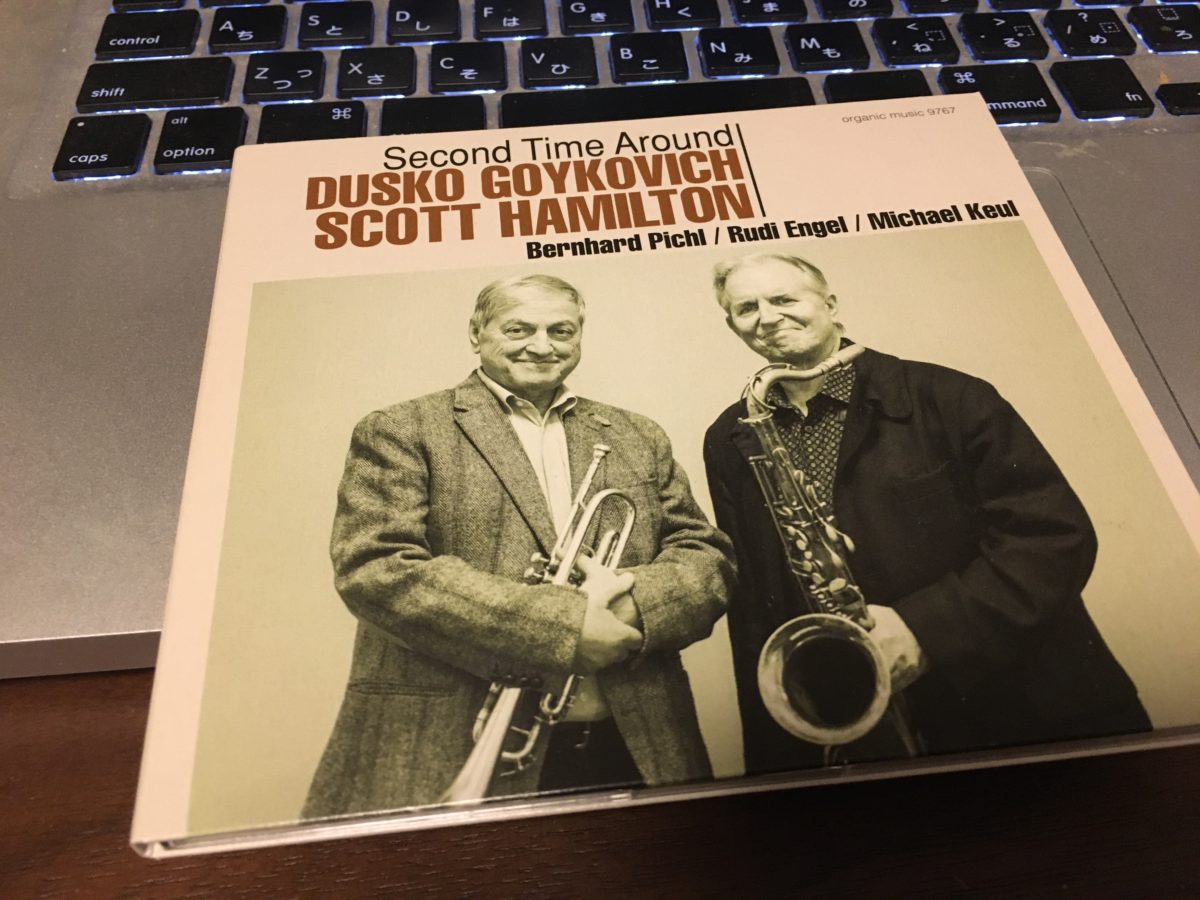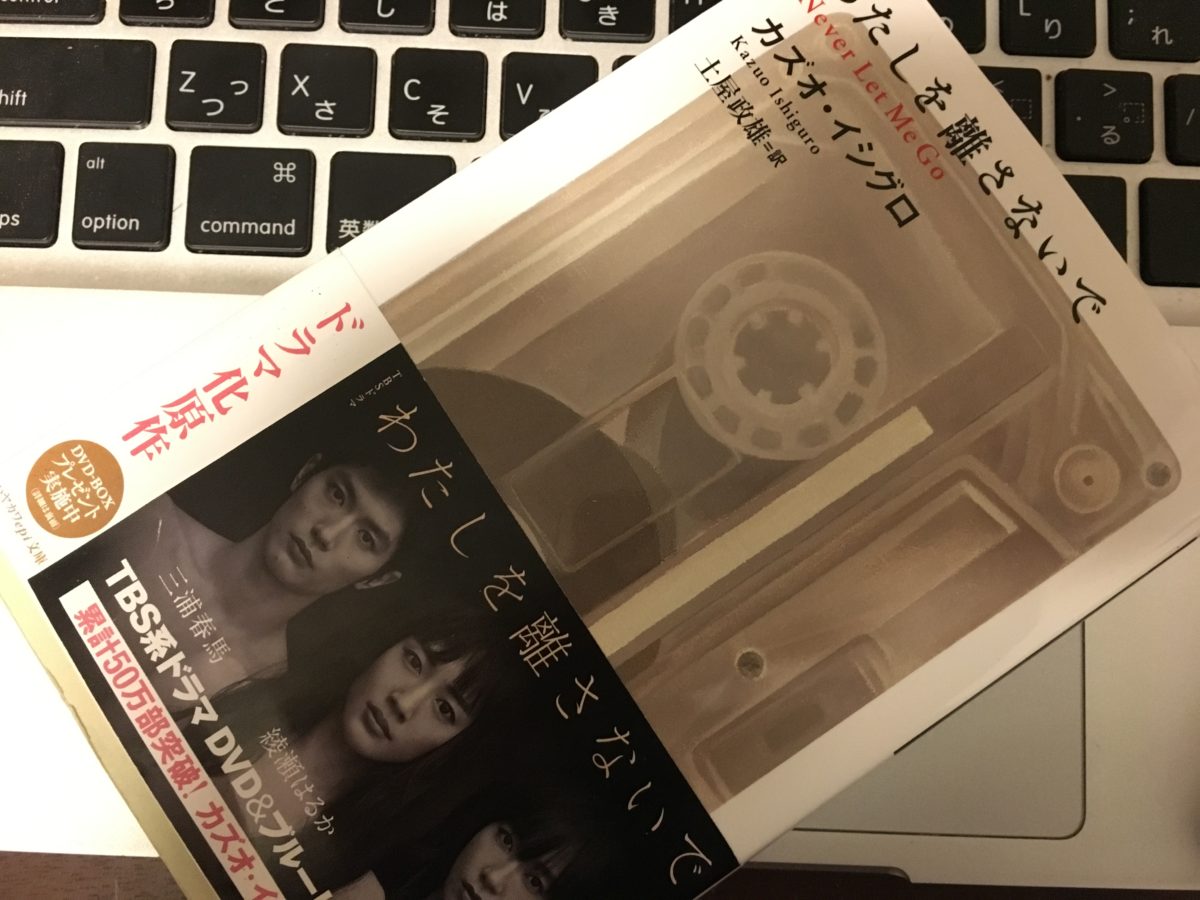良いアルバムなんだけれども、どうもはっきりと人に「良い」と言って勧められないアルバムというのがある。特に、ジャズのCDにある。
どういうアルバムかというと、「どうも胡散臭い」アルバムだ。
この「どうも胡散臭い」というのも様々なんだけれど、わたしが一番そう思うのは
「このアルバム、日本人向けに作ったんだろうな」
と思わせられるアルバムだ。
こういうアルバムは、結構多く存在している。まあ、世界の中で日本人が最もジャズが好きなんじゃないかと思うから(統計的な数字は知らないが)仕方がないのだけれど、プロデューサーが、日本市場を意識して作っているアルバムっていうのが結構たくさん存在する。
The great jazz trioとかChet Bakerの「Sings Again」なんていうのは、そもそも日本人がプロデュースしているからしょうがないけれど、そういう、もろ日本企画盤じゃないアルバムでも、この類のアルバムがある。
今日紹介するDusko Goykovich Scott Hamilton 「Second Time Around」もそういうアルバムの一枚だと思う。
Dusk Goykovichというトランペッターは、世界的にはどのくらい有名なのか、どのくらい評価されている人なのかは知らないけれども、日本人のジャズファン好みのトランペッターであることはまあまあ間違いないだろう。純粋に音楽的にどうなのこうなのという話を私がしても仕方がないけれども、まあ、平たく言うと「わかりやすい」ジャズを演奏してくれるトランペッターである。Tom Harrellとか、最近の若い売れっ子とは対極の、トランペッターである。
昔ながらの、間違いのないジャズを、かっちり演奏してくれるトランペッターと言える。
もう一人のScott Hamiltonだって、そういうサックス吹きだ。ハリーアレンと一緒にやっているテナーチームなんかのアルバムを聴いていてもそうだけれど、わかりやすい演奏を、昔ながらの古き良き”モダン”ジャズを間違えなく演奏してくれる。
こういうと、語弊があるかもしれないけれど、いかにも日本人のジャズファンが好きそうな演奏である。
それで、今日の「Second Time Around」である。
はっきり言って、アルバムとしては悪くないアルバムだ。有名なジャズのスタンダードばかり入っているし、ソロも、昔ながらのスタイルで、曲の解釈もこむづかしくない。聴いていて、全く疲れない演奏である。これはこれで良いもんだ。
しかし、なにかが物足りない。
私はこのアルバムのように完成されたパッケージよりも、どちらかというと、もう少し出来の悪い、完成度の低いアルバムを聴きたくなってしまう。プレスティッジの垂れ流しブローイングセッションとかそういうアルバムの方が聴いていて楽しい。決して名盤と呼ばれることのないアルバムでも、聴いていて刺激があって良い。
このブログのテーマは、都会の暮らしの中で疲れた時に聴ける音楽ということにしているから、この「Second Time Around」なんてうってつけなんだろうけれども、だからと言って手放しで素晴らしいと人に紹介できない。
お勧めできない、というアルバムを紹介しても仕方がないのだけれど、あくまでも、私の好みから行くと、お勧めしない。
しかし一方で、完成度の高い、聴いていて疲れない、リラックスできるジャズを聴きたい方には、うってつけのアルバムであることも確かである。
現に、このブログを書きながら聴いてみたりしたんだけれど、なんというか、とても素敵なアルバムである。抑制の効いた演奏にしても、アレンジの上品さでも、よくできたアルバムである。
とくに良いのは3曲目の「You’re my everything」この曲の可愛らしいところをうまいこと表現していて、素敵だ。なんといっても、最後のターンアラウンドのところが、カウントベイシー風の味付けがされていて、良い。ジャズの基本を押さえた、なんとも言えない名演である。
けれども、まあ、このアルバム、そういうアルバムですから。