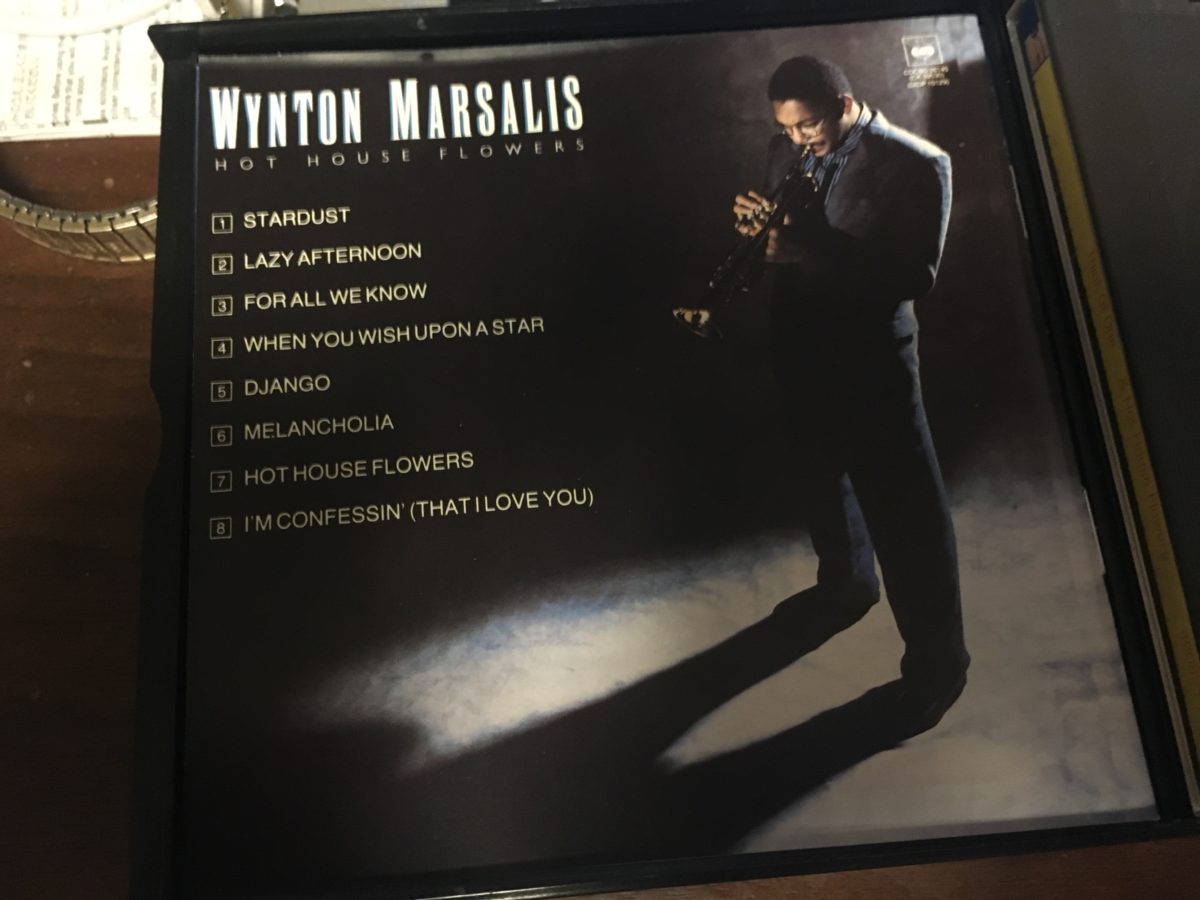私の本棚に古いGQのバックナンバーがあり、それの特集がJazzなのだが、見出しに「トランペッター不良論」と書かれている。
トランペッター、それも特にジャズのトランペッターには不良の印象を受ける人たちが多い。実のところはわからないけれど。
例えば、リーモーガンなんかは射殺された最期もなかなかドスが効いているけれど、若い頃から品行方正な雰囲気ではない。リーモーガンは17歳ぐらいでもう既にメッセンジャーズの花形だったわけだから、まあ、普通の一般人ではないから仕方ないかもしれないが、10代の頃からなんだかわけがわからんぐらいカッコイイ出で立ちで、スーツなんかの着こなしもピカイチである。専属のドレッサーが付いていたのかなと思うほど洒落ている。
洒落ていたらイコール不良というわけではないけれど、リーモーガンのスタイリッシュさはただのお洒落さんのセンスではない。ただならぬものを感じる。楽器も、初期こそはガレスピーのビッグバンドでみんなお揃いで吹いていたであろうマーチンのコミッティーを吹いているけれど、途中からコーンだとか、ホルトンだとか、まあ、吹奏楽部ではまず登場しないような楽器を手にしている。
あれが、カッコイイ。
リーモーガンの演奏についてはいろいろな好き嫌いもあるだろうからまあ、別の機会にするとしても、トランペッターにはそういうちょっと普通の雰囲気ではない方々が多いのは事実である。
その中の代表格といえば、私は何と言ってもフレディーハバードであると思っている。フレディーは、私の最も好きなトランペッターの一人なのだけれど、見た目とか格好とかはもちろん、そのアグレッシブでパワフルなトランペットのサウンドそのものから、品行方正なスクエアな人たちとは一線を画している。
まあ、フレディーハバードの私生活については私もよくは知らないのだけれど、体格は大柄で、ずんぐりしていて、リーモーガンのようなキリッとした感じとはちょっと違う。それでも、フレディーハバードがいつも、ジャズトサイズのスーツをパリッと着こなして、ステージにたつ姿は確かにカッコイイ。ノッチドラペルのダブルのスーツという、その辺に吊るしでは売っていないであろう背広、あれがまたなんだかただならぬ貫禄がある。ピークドラペルのダブルのジャケットであれば、40年代からジャズミュージシャンが着こなしているイメージがあるけれど(50年代はピチピチのラペルの細いスリーピースのシングルが多い)ノッチのダブルの背広を着ているのはフレディーぐらいだろうか。
使っている楽器もカリキオだとか、コーンだとか、ビッグバンドのセクションでは浮いてしまいそうな個性的な「明るい」音がするトランペットを吹いている。
その、カリキオとかコーンとかで、ダークなサウンドを出したり、パリッとしていて煌びやかなハイノートを吹いたりしている。フレディーハバードはオープンで吹いていてもすぐにフレディーだとわかる独自の音を持っている。その、存在感たるやなかなかのものである。私は、トランペットについてそこまで詳しいことはわからないけれど、おそらく、彼の音はクラシック音楽とかのトランペッターに言わせるととんでもない流儀なのではないかと思われているだろう。ハイドンとかバッハとかを吹いているモーリスアンドレのトランペットとかとは別の楽器のようである。
彼の、ミュートプレイもまた味わい深い。フリューゲルホルンの図太い音も素敵だ。世の中に、カッコイイジャズのサウンドというもののスタンダードがあるとしたら、それはフレディーのトランペットのサウンドだと思う。(ちなみに、ビリージョエルの「ザンジバル」のトランペットソロはフレディーハバードだ)フリューゲルホルンは、いろいろと持ち替えているようなので、詳しいことはわからないのだけれど、YouTubeでよく見かけるのはゲッツェンのエテルナ、「First Light」のジャケットに写っているのはケノンの楽器であるようだ。
フレディーは生前、インタビューでディジーガレスピーやら、チャーリーパーカー、コルトレーンなんかを引合いに出されて、そういうジャズジャイアンツの一員としてどうですか?みたいな質問をされた時に、「私は、そんな大物と一緒に肩を並べられるのは照れ臭い、自分はただラウドにトランペットを吹いてきただけだよ。」と答えたらしいが、そういう謙虚さも含めてなんだか私の理想のトランペッターなのである。ただの出しゃばりではないトランペッター。よっぽど自信があったのだろう。
フレディーのひたすらビッグでラウドなトランペットを聴いていると、なんだか少しホッとするのも事実である。
私は、学校に行っていた頃、進学校に通っていたのだが、とにかく学校の成績が良くなくて先生だけでなく、同級生にも馬鹿にされていた。馬鹿だったのだから仕方ないのだが。あの頃、よくフレディーのオープンセサミを聴いて、気分を紛らわせていた。
不良にも、品行方正な優等生にもなれない中途半端な自分の悩みを、フレディーのラウドなトランペットの音がぶっ飛ばしてくれた。あの頃憧れた、フレディーハバードには、少しも近づけてはいないけれど、今夜も聴いている。