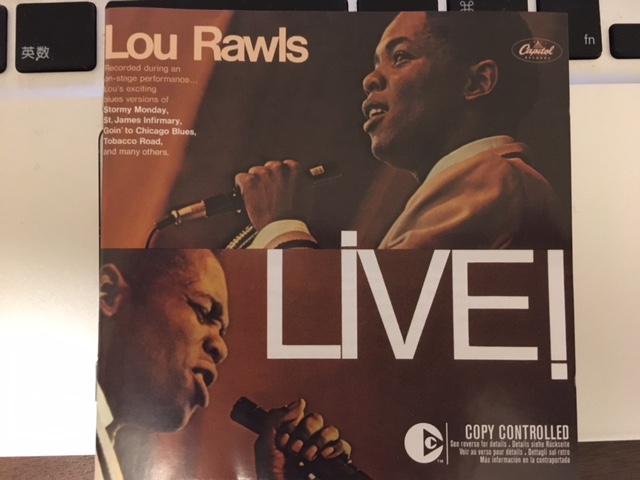東京に住むようになって17年になる。最初の6年間は国立市に住んでいた。23区内ではなかったけれど、私のような田舎者にとっては十分東京である。札幌に住んでいた頃は、茨城、群馬あたりまでは東京という認識だった。その認識は今でもあまり変わらない。
上京してきた頃と、この街の印象はあまり変わらない。新宿、渋谷、池袋、銀座、六本木どこもここ17年間でさほど変わったという印象は受けない。もちろん、東京スカイツリーや、六本木ヒルズを始めとする新しいランドマークは建ったけれども、そんなものは人波、繁華街、住宅街に埋め尽くされた東京という大きなイメージをほとんど変えることはない。
東京は大きな繁華街が数珠つなぎにいくつもあり、その周りにどこまでも果てることのない住宅街が連なっている。駅と駅の間で家並みは途絶えることなく、山手線、中央線、京王線、小田急線その他ほとんどの電車が、家並みの隙間を切り裂くように走っている。これほど電車・地下鉄網が発達した街も珍しいだろう。
そんな東京を写した写真集を紹介したい。
内堀晶夫の「街 Tokyo 1976−2001」という写真集を見た。
20cm角ぐらいの、比較的小ぶりな写真集だ。見開き両ページに1点ずつ掲載されているので、写真の点数は多い(70枚ぐらいか)。小さな写真集のわりに見ごたえのある本である。
東京の街角でのスナップ写真が載っている。街で人物を撮った写真である。一枚一枚の写真の説明はとくについていないので、いつどこで撮られた写真なのかは、写真から推し量るしかない。だいたいどのあたりで撮られたのかがわかる写真もあるのだが、どの写真も私の知っているような東京の姿ではない。
この本の「街 Tokyo 1976−2001」というタイトルから、写真はおそらく1976年から2001年の間に撮られたものだと思う。私が東京に来たのは2000年のことだから、ほとんどの写真は私の知らない時代の東京だ。そういう前提で見ても、ここに写っている街はどれも違和感がある。妙に古い感じがするうえに、どこか異国の街の日常を垣間見ているような気がする。私の住んできた東京はこんな風な違和感のある「生活感」はない。こんなではない、もっとなんでもない日常、一言で言うとつまらない街である。この写真集に登場する街も、あんまり楽しい街ではなさそうだけれど。
巻末に添えられている文章によると、この写真家は東京都国分寺市に住むサラリーマンとのことだ。そう言われると、立川の写真が何点か載っていた。
こういう写真を見ると、東京っていう街は人によってずいぶん見え方が違うんだと思う。ここに住む人にとって、それぞれ街の見え方は大きく変わるんだろう。私の東京の見え方は地方出身者の視点からのものなのかもしれない。泉谷しげるが
ものめずらしい見世物はすぐ飽きて、自分だけが珍しくなってく
と歌っていたけれど、確かに、東京に住むようになって17年目でも、未だに自分はこの街から浮いてしまっているのではないかと恐れることがよくある。自分だけが特別というのとも違う、自分が「遅れている」というような感覚か。
巻末に内堀晶夫さんは長野のご出身だと書かれているけれど、同じく東京の出身ではない自分に、東京はこんな風には見えない。
まあ、この写真集で提示されている東京は、この写真家に東京がどう映っているかではなくて、写真が東京をどう捉えたかであるということは言えるんだけれど。それでも、ここに写っている東京は異国の街のようだ。