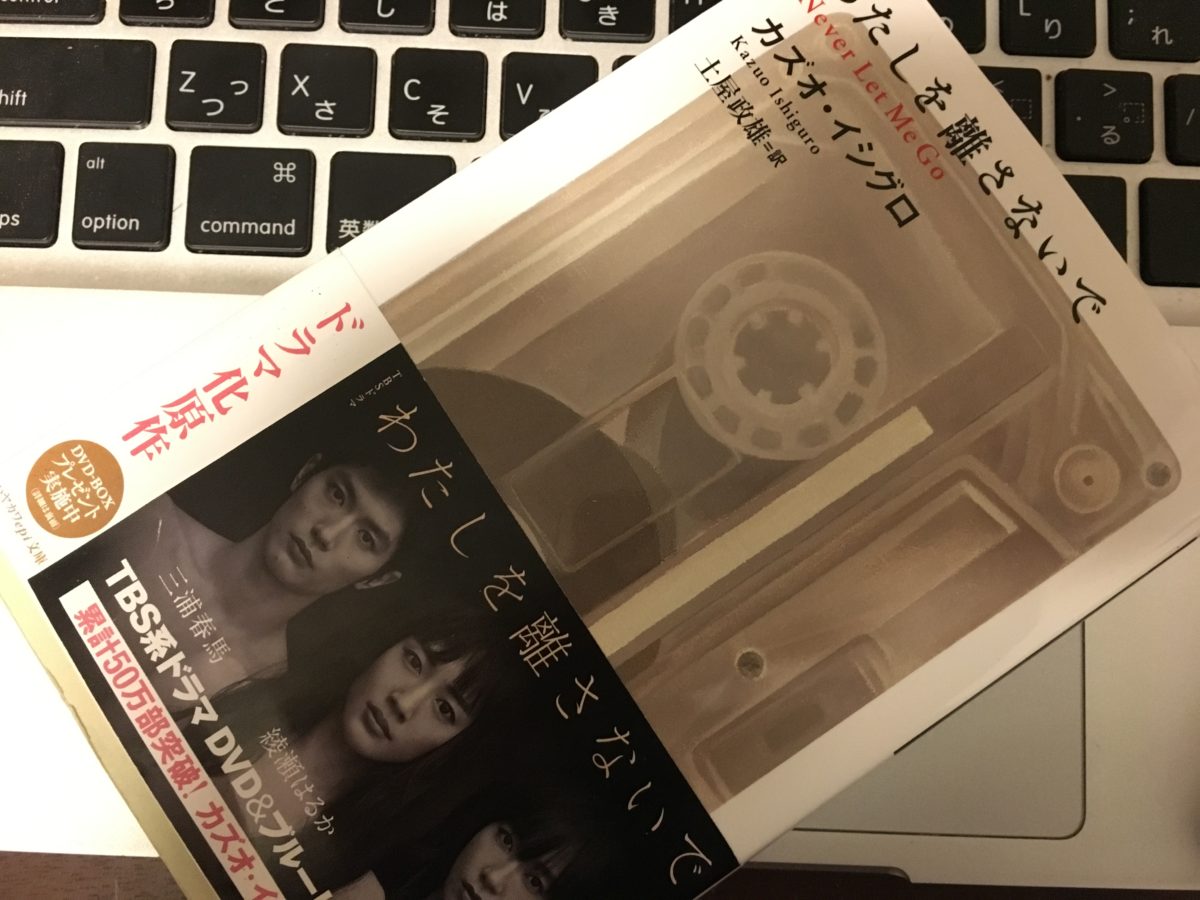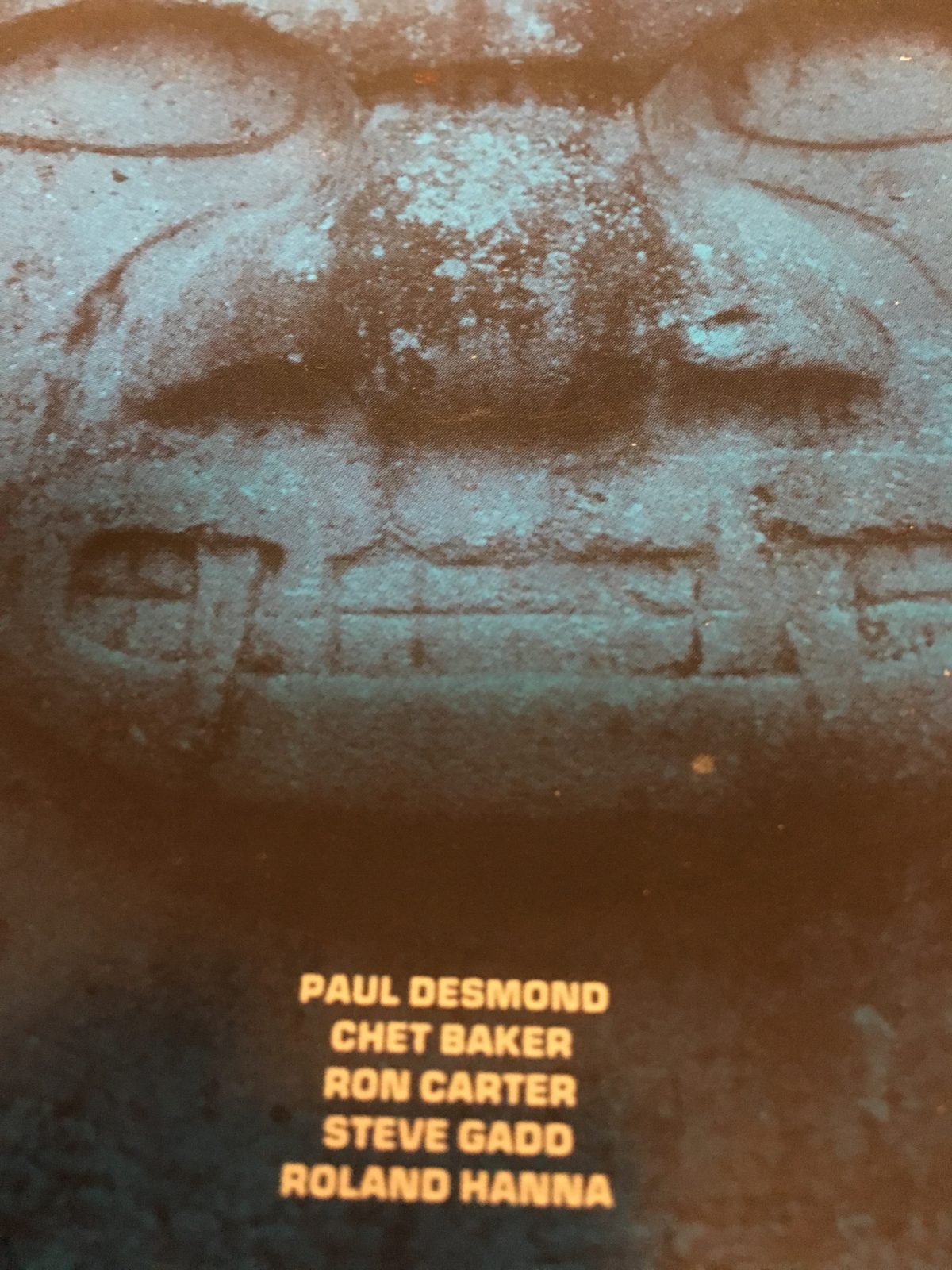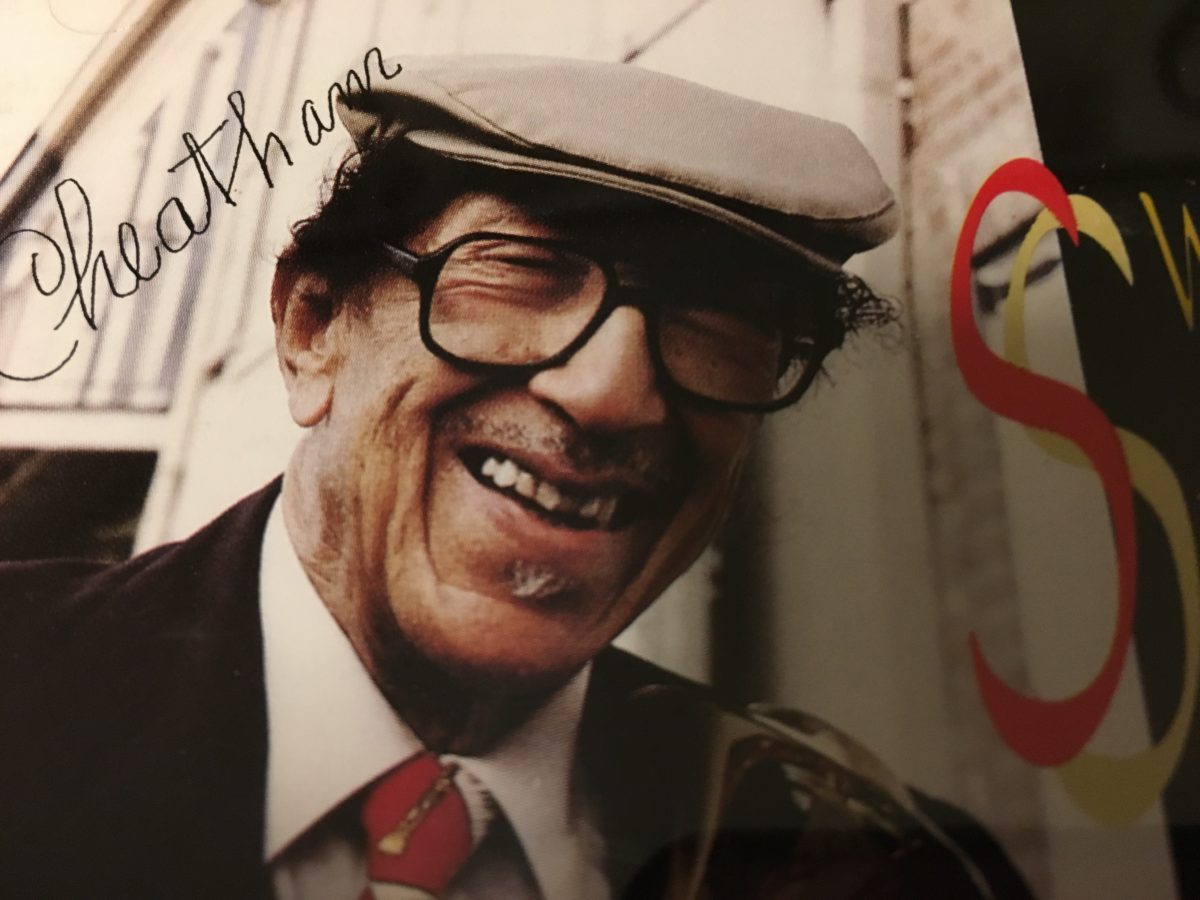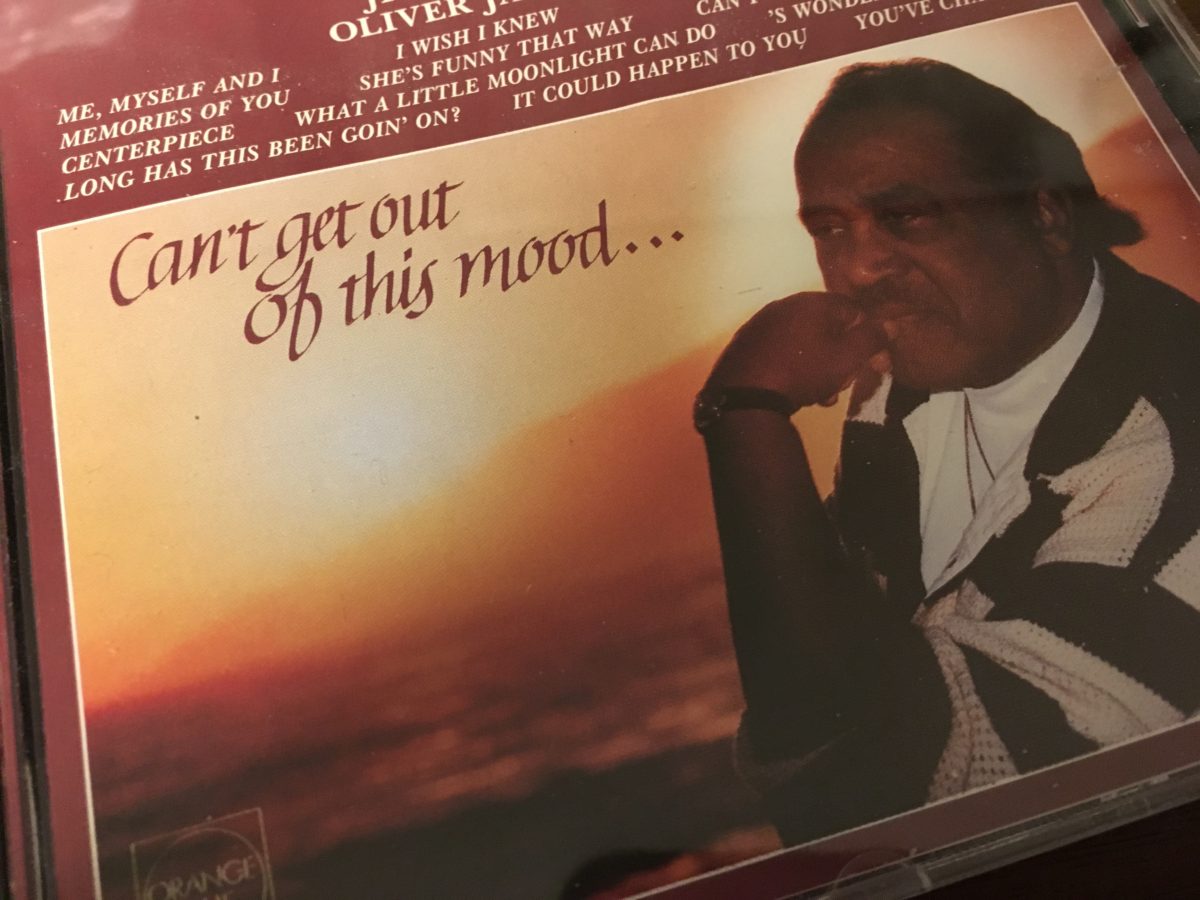ノーベル平和賞だのなんだのにあまり興味はないけれど、やはりノーベル賞はすごいことだけは知っている。
ノーベル文学賞、などというと、それがどれぐらいすごいことなのかわからなくなってしまうくらいすごいものなんだろう。それは、川端康成、ガルシアマルケス、大江健三郎なんかの、数少ない私が読んだことのあるノーベル文学賞受賞者の顔ぶれをみても明らかである。
とくに川端康成は、すごいと思う。世界に何編の小説があるのか、私には見当もつかないが、まあ、数えて数えられる以上に現存することは確かだろう。星の数ほどという表現があるけれども、まさに星の数ほど、世の中には小説というものがある。
例えば、八重洲ブックセンターに行く。あそこにはそれこそ数え切れないほどの書籍が置かれており、9割9部9厘の本は読んだことのない本だ。その中の1割ぐらいが、小説やら文学という範疇に収まる本で、それだけを採ってみて、全て読んでみろと言われても、おそらく一生かけても読むことはできないだろう。しかし、忘れてはいけないことは、あそこに置かれている文学も、世界に現存する小説、文学のほんの一部であるということだ。
その証拠に、私は何度かあの店で中上健次の本を探しに行って無かった、という経験がある。中上健次に限らず、福永武彦、堤中納言物語もそうだった。無かった。
中上健次、福永武彦などと言ったら、文学の世界では大家である。その、大家の本ですら無い。いや、探したらあったのかもしれないけれども、見当たらなかった。いわんや、大家では無い方々の作品のこと、日本語に訳されていない海外の文学に思いをはせると、それこそ、八重洲ブックセンター50軒分以上の文学というものがこの世に存在するであろう。
その中でも、川端康成は特別なんだから、すごいと思う。数多ある文学の中から、「ノーベル文学賞」をとっちゃったんだからすごい。
なにも、ノーベル賞をとったから川端康成がすごいというのでもない。あまり本を読まない私の中でも、川端康成は特別にすごいと思う存在だ。彼の作品は何度もなんども読むたびに新たな発見がある。それだけでは無い、読むたびに心を惹くものがある。人をして、感動させる何かがある。それがいったいなんなのかがわからないのだけれども、とにかく強く惹きつけられるものがある。
生きていて、川端康成の作品に出会えてよかったと思う。夏目漱石の草枕だって、素晴らしい作品だと思うけれども、川端康成のほうが上だと思う。文学に上も下も無いとおっしゃる方もいると思うけれど、それでも、川端康成のほうが上だと思う。
それで、ノーベル文学賞である。
イシグロカズオ、もといカズオ・イシグロがとったらしい。かずお・楳図ではなく、カズオ・イシグロがとったらしい。あの、日の名残りのカズオ・イシグロである。
「わたしを離さないで」(原題Never let me go)を読んだ。
世の中では、村上春樹がとるんじゃないか、とか毎年騒がれるが、村上春樹がとるなら、その10年前にカズオ・イシグロがとらないとおかしいだろう。Never let him go!とカズオ・イシグロに叫ばれているような衝撃を受けた。
単なる気味の悪い小説とも捉えられるこの一編の中には、一貫したものがある。一貫性ではなく、一貫し、話を突き動かすものがある。それがなんなのか、言葉で言えるのであれば、この小説など読まなくてもいいだろうけれど、私にはそれがなんなのか言い表わせるボキャブラリーが無い。
あえて言うならば、それは、不安という言葉であろうし、腰掛の人生に対する肯定とも言える。自分という存在を肯定することの果てども無い戦い、そしてその戦いの虚しさ。そういうものがこの小説にはある。それが、ここで私の言っている一貫しているものと同じものでは無いのかもしれないけれど、ある意味ではそうだとも言える。いや、そう言いたい。
そう言い切りたいが、そう言えない。そういうもどかしさを含んだ人生そのもに対するどうでも良さと切実さ、それがこの小説にはある。
この際、主人公の置かれている特別な境遇は一度置いておこう。それでも、そこには誰もが持つ自分を肯定したいという飽くなき欲求と、肯定したところでどうということでも無いという虚しさがはっきりと描かれている。それは、すべての登場人物に共通しているようで、いや、まあ、共通しているのだけれども、それぞれに違った立場からその足元の不安定さが滲み出てきている。
これが、仮に普通の境遇の人の話だったとしよう。そうしたところで、この話そのものが私に訴えかけてくるメッセージはそれほど変わらないのかもしれない。
けれども、この小説の持つ独特の世界観、主人公たちの持つ境遇、普通の人生では無い人生が、まるで鏡のように私たち「普通の人」たちを映し出す。それも、かなりいびつな形に、不自然な形に、特権階級の人達として映し出す。
この小説は、他の多くの小説同様にいびつな鏡なのである。私を映し出すいびつな鏡。
この小説はそこだけでも、十分に成り立つ作品なのであるが、そこに留まらず、懐かしさを超えた気味の悪さが存在する。その気味の悪さも同様にこの小説を貫いている。気味の悪い小説というものは世の中にたくさんあるのだろうけれど、この小説に説得力があるのは、その気味の悪さの原因は読者自身にあるということを初めから投げかけてくることだろう。
まあ、それ以上書いてしまうとこれからこれを読む人たちに悪いから、書かない。それと、これほどまでに完成された作品について、何かこれ以上言える言葉を私は知らないから。