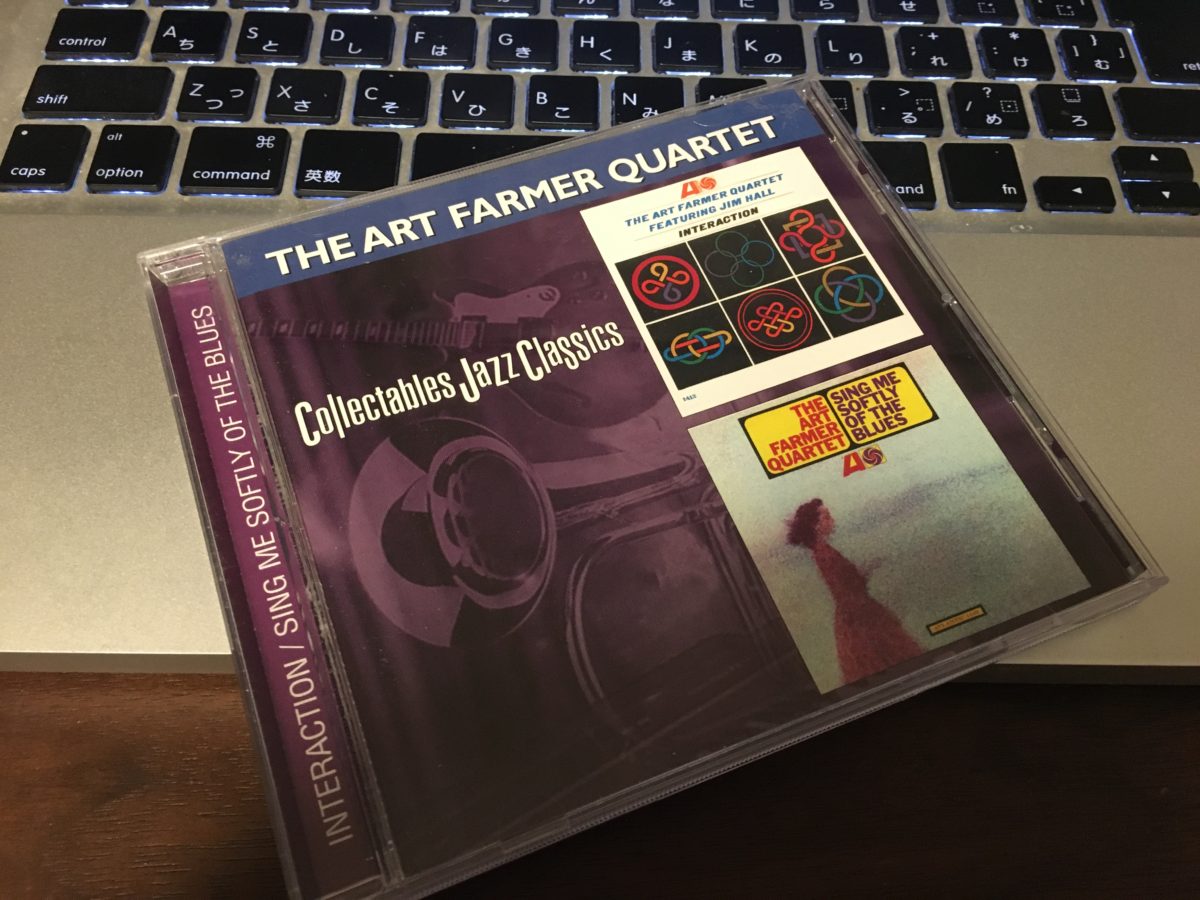近頃落ち着いて家のステレオで音楽を聴くような時間がない。時間がないのは仕事が忙しいせいとか、何か他に夢中になっていることがあるとか、そういったことではなく、自宅にいる時間の大半を寝ることに費やしているからだ。
そのために、家で音楽を聴くことや、楽器を練習したりすることがほとんどなくなった。休みの日などは、一日中予定もなく、言ってしまえば暇なのだが、暇な人間は大抵何もしない。暇な人間は体を動かそうとしない。暇な人間は生産的な活動をしない。何にもしないくせに、やけに「時間がもったいない」などと考えて、何かをしようとして、やはり無駄な時間を過ごしてしまう。
私は、暇なときはやはり何もせずに、ほとんどを昼寝の時間に費やしている。楽器を練習したり、音楽でも聞けば良いものなのだが、そういうこともしない。本を読んだりもしない。全くこれでは、なんのために生きているのかがわからない。楽器の練習もしない、音楽も聞かない、本も読まない。そういうことではろくな人間にはならない。
かつては、かなり熱心に音楽などを聴いていた頃があって、自宅には約3000枚のCDと1000枚近くのレコードがあるのだけれど、これも、最近はめっきり聴いていない。ちょっと前までは「愛聴盤」なるものがあって、毎日のように繰り返し繰り返し聴いていた。Bobby Darinの死後編集されたベスト盤「Darin」やら、 Frank Sinatraの「L.A. is My Lady」なんかは大好きで、それこそ盤が擦り切れるほど聴いた。ビリージョエルの古いアルバムも好きでややベタではあるが「Stranger」なんかも、腐るほど聴いた。
しかし、最近はそれらのレコードもほとんどターンテーブルに乗せることはない。CDも聴かない。音楽といえば、通勤の時にiPhoneで聴く程度か。
しかし、iPhoneで聴く音楽はどうも味気ない。家のオーディオセットで聴く音楽のような「音楽を聴いている感」に乏しい。iPhoneに音楽を入れてしまうと、どうも小さなイヤフォンで聴くように音質がなってしまうせいか、なんだかどれもこれも同じような音楽になってしまう。特に、ドラムやシンバル、ベースの音がほとんど聞こえなくなってしまい、歌やらギターやらうわものばかりが聞こえてきて、音楽を聴くというよりは、音楽を「確認する」作業になってしまう。私の好きなRhodesピアノの音なんかはCDやらレコードで聴くとくっきりと聞こえてくるのだけれど、iPhoneで聴くとなんだかジワジワ、モゴモゴ聴こえてきてしまい、喜びにかける。レコードやCDなどはミキシングの芸術のようなもんなんだから、iPhoneで聴いてもちっともそういう妙味は味わえない。
家のステレオも、そんなに立派なセットを組んでいるわけでもないけれども、最低限そういうミキシングの妙味が味わえるセットにしている。
そんななか、iPhoneでほとんどまともに聞こえなくて残念なのがRichard TeeのRhodesの音だ。先ほども書いたがRhodes pianoの音が好きな私は、ロックのレコードなんかに入っている彼のRhodesの音を聴くとなんだかウキウキしてくる。有名なところではビリージョエルの「Just the way you are」のイントロ、あれが彼の音だ。 Paul Simonの名曲「Still crazy after all these years」のイントロもRichard Teeが弾いている。私は、この2曲のイントロを弾きたいがためだけにRhodesを持っているようなもんなのだ(Still crazyの方は未だに弾けないが)。
彼は恐らくそれらのトラックではFender RhodesをフェイザーSmall Stoneに繋げて弾いているのだけれど、スピーカーはローズのスピーカーから鳴らしているのか、それとも外付けのアンプで鳴らしているのか、いまいちわからない。そもそも、フェンダーローズを殆ど触ったことがないので、果たしてSmall Stoneをつなぐだけでああいう音が出るようになるものなのかどうなのか確認したことはない。
自宅の機材も、Richard TeeにならってFender RhodesとSmall Stoneにすれば良いようなもんなのだが、たまたまRhodes MK1が安く手に入り、それの音が気に入ってしまったので、Rhodes MK1にMXRのPhase 90(これも70年代後期のもの)を繋げて使っている。Small StoneだとなんだかRichard Teeのあの音が出せそうな気もするのだけれど、エレハモのエフェクターはちょっとかかりが強いのが好みではないので、かかりが弱い70年代の MXRにした。
リチャードティーのローズサウンドは上に書いたようなポップスのレコードもさることながら、Stuffのアルバム、Gadd Gangのアルバムでも堪能できる。私は Stuffのファンでも、スティーヴガッドのドラムが好きなわけでもないのだけれど、リチャードティーのローズの音を聴きたいが為だけに何枚かアルバムを持っている。けれど、Stuffのアルバムを聴くとどうしてもRhodesの音ではなく彼のスタインウェイピアノのキリッとした音に耳を奪われてしまう。クラシックのピアニストはあんなに硬質な音を求めないだろうけれど、 Richard Teeの音楽にはどうしても、あのピアノの音が不可欠なような気がする。まあ、もっとも、スタッフの録音の時はなんのピアノを使っていたかは不確かだけど(ライブ盤ではCP−80をつかっていたりするから)。
80年代の名曲のイントロは殆どがRichard TeeのRhodesピアノから始まると言っても過言ではないぐらい、彼の音は印象的でRhodesという楽器の魅力を十分に引き出していると思う。
リチャードティー、一度で良いから、生で彼のRhodesを聴きたかったな。